
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
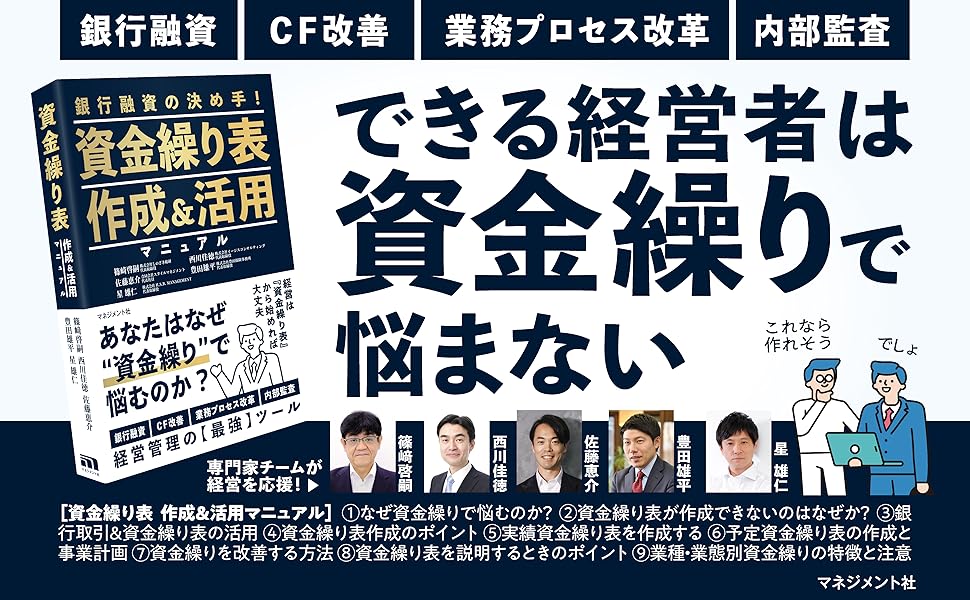
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
B/S(貸借対照表)で「実態の体力」を把握した後、
銀行は次にP/L(損益計算書)で「本業の持続性(稼ぐ力)」を確認します。
前述の通り、P/Lの利益額そのものはそのまま信用しませんが、
「どのような事業活動の結果、その利益(あるいは損失)が生まれたのか」というプロセスを重視します。

銀行員はP/Lのどこを見るのか?
ポイント1:営業利益・経常利益
P/Lには5つの利益(売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益)がありますが、銀行が最も重視するのは「営業利益」と「経常利益」の2つです。
- 営業利益(本業の儲け):
これがマイナス(営業赤字)ということは、本業を行えば行うほど赤字が膨らむ状態を意味します。これは事業の根幹に関わる重大な問題であり、銀行は極度に警戒します。 - 経常利益(本業+財務活動の儲け):
営業利益が黒字でも、借入金の利息負担が重すぎて経常利益が赤字になるケースがあります。これは「稼いだ利益が利息に食いつぶされている」状態であり、返済能力に疑問符がつきます。 - 当期純利益は重視しない:
「特別利益(不動産売却益など)」や「特別損失(在庫処分損など)」で大きく変動する「当期純利益」は、一時的な要因が強いため、銀行はあまり重視しません。本業の力を示す営業利益・経常利益が黒字であることが絶対条件です。
ポイント2:減価償却費
これは、銀行の視点と節税の視点が真っ向から対立する項目です。
節税のために利益を圧縮したい場合、減価償却費は上限まで計上します。逆に、赤字を回避して黒字に見せたい場合、減価償却を任意計上(または計上しない)という選択をする経営者がいます。(このケースは顧問税理士からの助言もあり、よくあるケースです。)
銀行は、この「利益操作」を見逃しません。 彼らは、会社が正規のルールで減価償却費を計上していたら「実質利益」はいくらになるかを必ず計算し直します。減価償却で利益を調整している(=粉飾)とみなされた決算書の信用力はなくなります。
ポイント3:売上高の推移
銀行は単期のP/Lだけを見ません。
必ず過去3期分を比較し、「トレンド(どのように変化しているのか)」を見ます。
- 利益が同じ1,000万円でも、「増収増益(売上5億→6億)」と「減収増益(売上7億→6億)」では、評価は全く異なります。
- 前者は「事業が成長している」とプラス評価されますが、後者は「コスト削減で無理やり利益を出した(ジリ貧)」とマイナス評価されます。
もしくは、6億でも同じ利益を出すことができた、という点は評価されるかもしれません。
売上は事業の勢いを示すバロメーターです。本業が市場に受け入れられ、成長しているかどうかが厳しく見られています。
ポイント4:経費(役員報酬・3K・戦略経費)
経費の中身も精査されます。特に以下の項目は要注意です。
- 役員報酬:
会社の体力(利益)に見合わない、過大な役員報酬が設定されていないか。社長が会社を私物化していると判断されます。 - 経費の3K:
銀行員の間で俗に言われる「3K」=「接待交際費」「交通費(出張費)」「会議費」が過大でないか。これらは利益操作や私的流用の温床になりやすいため、厳しくチェックされます。 - 戦略経費:
「広告宣伝費」「販売促進費」「接待交際費」「旅費交通費」など、売上アップ・利益アップさせるための経費がどれだけ使われていて、それがどれだけ費用対効果が出ているのか?を見ています
なぜ銀行格付け(債務者区分)が重要なのか?
銀行は、決算書(定量評価)と事業内容(定性評価)を分析し、全ての融資先を5段階で「格付け(債務者区分)」します。
この格付けは、あなたの会社の「通知表」そのものです。 この格付けによって、融資の可否、金利、貸出枠、さらには既存融資の扱いまで、すべてが決定されます。
- 正常先:
財務内容良好。業績も安定。銀行が最も積極的に融資をしたい先。 - 要注意先:
財務内容に問題がある(例:赤字傾向、債務超過ではないが純資産が薄い)。金利が引き上げられたり、融資条件が厳しくなったりする。 - 破綻懸念先:
実質債務超過である、または赤字が継続し返済が困難。原則、新規融資は不可。銀行は担保保全や融資の回収(フェードアウト)を検討し始める。 - 実質破綻先:
経営が実質的に破綻しており、再建の見込みがない。 - 破綻先:
倒産・法的整理となった先。
経営者が目指すべきは、何としても「正常先」を維持することです。「要注意先」に転落した時点で、一気に資金調達が厳しくなります。そして「破綻懸念先」(=実質債務超過)と格付けされたら、銀行からの資金調達ルートは実質的に絶たれたと考えてください。
融資評価を上げるために経営者が今すぐできる5つの対策
では、銀行の「見方」を踏まえ、彼らの評価を上げ、融資を引き出す「強い決算書」を作るにはどうすればよいでしょうか。
これは税理士に任せきりでは実現できません。節税とは異なる「財務戦略」として、経営者自身が主導して実行する必要があります。
対策1:とにかく「現金・預金」を増やす(月商3ヶ月分目標)
銀行評価の最重要項目は「現金・預金」です。
これが全ての基本です。
- 利益が出たら納税し、残りを内部留保(現預金)として貯める
これが王道です。過度な節税(無理な経費利用)で現金を社外流出させるのは、融資戦略上は最悪の選択です。 - 不要な資産は売却し、現金化する
私がコンサルティングしたある建設会社では、社長の趣味で保有していた高級車の売却、使っていない保養所(不動産)の売却、保険積立金の解約、上場企業の投資有価証券の売却をしてもらいました。B/S上では資産が減りますが、「現金・預金」が増えるため、銀行の評価は劇的に改善しました。
対策2:「役員貸付金」をゼロにする
銀行評価の「がん」である役員貸付金は、1円たりとも許容してはなりません。即時解消してください。
- 役員報酬から相殺する(社長個人の手取りが減りますが、会社の信用が上がります)
- 社長個人が銀行や親族から借りて、会社に返済する
- 退職金と相殺する
いずれにせよ、税理士と相談し、決算書からこの勘定科目を消し去ることが急務です。
もし、売却できない場合には、今後、どのように役員貸付金を解消していくかの計画を書面にまとめ、銀行に提出しましょう。
対策3:「役員借入金」は返済しない(むしろ増やす)
逆に、プラス評価となる「役員借入金」は、会社の現金・預金が減るため、安易に返済すべきではありません。
- これは「実質資本」としてB/Sに残しておきましょう。
- どうしてもB/Sを綺麗にしたい場合は、税理士と相談し、現物出資(DES:デット・エクイティ・スワップ)として「資本金」に振り替えることで、債務超過を解消し、自己資本を厚く見せることが可能です。
対策4:勘定科目内訳明細書をクリーンにする
B/S(貸借対照表)を「実態」で綺麗にすることが重要です。
- 不良在庫、回収不能な売掛金、使途不明な仮払金は、決算前に「特別損失」として処理(損切り)し、B/Sから膿を出し切ります。
- 一時的に「当期純利益」は赤字になりますが、B/Sがクリーンになることで、銀行は「この経営者は自社の課題を正確に把握し、手を打っている」と誠実性を高く評価します。
- 膿を隠したままの「見せかけの黒字」より、膿を出し切った「実態の赤字」の方が、翌期以降の融資戦略においてはるかに有利です。
対策5:事業計画書と資金繰り表をセットで提出する
決算書は「過去」の成績表にすぎません。銀行が知りたいのは「未来(=返済できるか)」です。
- 決算書(過去)が赤字であっても、それをどう改善するかを示す「事業計画書(未来)」があれば、評価は逆転できます。
- 特に「資金繰り表」をセットで提出することは極めて有効です。
- 「社長が自社のキャッシュフローを正確に管理・把握している」という姿勢を見せるだけで、銀行員の心証は劇的に改善します。「この社長なら、融資した資金も計画的に使ってくれる」という信頼に直結するからです。
まとめ
銀行は、あなたの会社の「将来性」と「誠実性」を見ています。 彼らが見ているのは、利益の額面ではなく「実態の資産(特に現預金)」と「本業の持続性」です。
節税(税務)と融資(財務)は、目的が全く異なります。 融資を最重要戦略と位置づけるならば、税理士任せにせず、「現金・預金を厚くし、B/Sをクリーンにする」ことを最優先にしてください。
銀行の視点を理解し、彼らが安心できる「実態」の決算書と「未来」の計画書を提示することこそが、盤石な資金繰りを実現する唯一の道です。
決算書の「銀行の見方」に関するFAQ(よくある質問)
Q1. 赤字決算だと、絶対に融資は受けられませんか?
A1. いいえ。赤字の「理由」によります。例えば、赤字理由が「先行投資(広告費増、採用増)」や「不良在庫の一掃(特損計上)」など、未来の黒字化に繋がる合理的なものであれば、事業計画書と合わせて説明することで融資は可能です。最も良くないのは、本業(営業利益)で赤字が慢性化している(2期連続、3期連続で赤字になっている)状態です。
Q2. 銀行は決算書の他に何を見ていますか?
A2. 決算書以外の「定性情報」も重要視します。具体的には「経営者の人柄・ビジョン(事業計画書)」「(試算表の提出など)銀行への報告姿勢」「本業の将来性(業界動向)」です。これらを合わせて「事業性評価」といいます。また、社長個人の信用情報(CIC)・個人資産も確認されます。
Q3. 決算書は税理士に任せきりでも大丈夫ですか?
A3. 危険です。多くの税理士は「税務(節税)」のプロであり、「財務(融資)」のプロではありません。節税を優先しすぎた決算書(過度な経費計上、役員報酬設定)は、銀行評価を下げる可能性があります。経営者自身が銀行の視点を理解し、税理士と「融資に強い決算書」について相談することが不可欠です。
Q4. 融資の相談はいつ行くのがベストですか?
A4. 「お金が足りなくなりそう」な時ではなく、「業績が良く、お金が足りている」時に行くのがベストです。銀行は余裕のある会社に貸したいものです。決算書が黒字で着地した後、その決算書を持って「今後の事業拡大のために」と相談するのが最も良いタイミングです。