
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
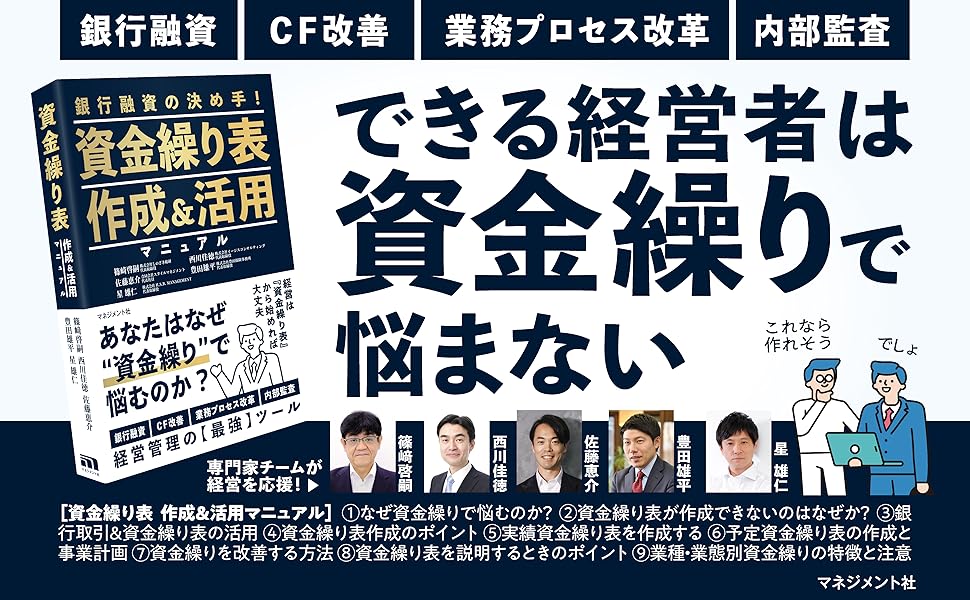
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「今月も売上が順調に増えた。利益も出ているはずなのに、なぜか月末の支払いが苦しい…」
「銀行に融資を相談したら、『キャッシュフロー計算書はありますか?』と聞かれて困ってしまった…」
「そもそもキャッシュフロー計算書って、資金繰り表と何が違うの?」
財務コンサルタントとして長年、多くの中小企業経営者様とお話しする中で、この「利益と現金のズレ」は最も多い悩みのひとつです。
このズレを放置した結果が、いわゆる「黒字倒産」です。
帳簿上は黒字でも、手元の現金(キャッシュ)が尽きた瞬間に、企業は倒産してしまいます。
この最悪の事態を防ぎ、会社のお金の流れを正確に把握するために不可欠なツールが、「資金繰り表」と「キャッシュフロー計算書(C/S)」です。
しかし、多くの経営者様がこの2つの違いを混同されています。 この記事では、「なぜ現金が残らないのか」という謎を解く鍵となる2つの書類について、その決定的な違いから、実務的な作り方、そして最も重要な「連携」や「活用法」まで、専門家の視点で徹底的に解説します。
資金繰り表は「未来の天気予報」、C/Sは「過去の健康診断書」
まず、この2つの根本的な違いを理解してください。
- 資金繰り表 = 未来のお金の流れを見る「天気予報(予測)」
- キャッシュフロー計算書(C/S) = 過去のお金の流れを分析する「健康診断書(実績)」
どちらも「現金(キャッシュ)」に着目する点は共通ですが、見ている時間軸と目的がまったく違います。
一目でわかる比較表
両者の違いを表にまとめました。
| 項目 | 資金繰り表 | キャッシュフロー計算書 |
| 時間軸 | 過去~未来 | 過去 |
| 目的 | 資金ショートの回避 | 経営活動(営業・投資・財務)の分析 |
| 主な利用者 | 社長、経理担当者(内部向け) | 社長、銀行、投資家(外部向けも) |
| 作成義務 | なし (ただし経営には必須) | 上場企業は義務 (中小企業は任意) |
| 形式 | 自由(Excel管理が一般的) | 厳密な会計ルールあり |
資金繰り表とは?(未来の天気予報)
資金繰り表は、
「いつ、いくら現金が入り、いつ、いくら出ていくか、そしていくら残るか」を予測し、未来の現預金残高をシミュレーションする、唯一の資料です。
その最大の目的は、「資金ショート(現預金が底をつく日)を事前に察知すること」です。
天気予報が「3日後に台風が来ます」と警告するのと同じで、資金繰り表は「来月25日の支払いで現金がマイナスになりそうだ」というアラートを鳴らしてくれます。
アラートが鳴れば、「仕入先への支払いを待ってもらう」「銀行につなぎ融資を頼む」といった対策を、余裕を持って打つことができます。
キャッシュフロー計算書(C/S)とは?(過去の健康診断書)
キャッシュフロー計算書(C/S)は、P/LやB/Sと並んで、決算書(財務諸表)のひとつです。過去の一定期間(通常1年間)において、「なぜ」「どこから」現預金が増減したのか、その原因を分析する「結果報告書」です。
健康診断書が「体重が増えた原因は、食生活(営業)か、運動不足(投資)か」を分析するように、C/Sは「現金が増減した原因は、本業(営業活動)か、設備投資(投資活動)か、借入(財務活動)か」を突き止めます。
なぜ「損益計算書(利益)」だけではダメなのか?
多くの経営者様がP/L(損益計算書)の「利益」だけを見て安心し、現預金の不足に気づけません。なぜなら、会計上の「利益」と、手元の「現預金」は、発生と入出金のタイミングがズレるからです。
このズレを生む主な原因は3つあります。
- 売掛金・買掛金:
今月100万円売り上げても(利益発生)、入金が2ヶ月後なら、手元の現預金は増えません。逆に、支払いが1ヶ月後なら、今すぐ現預金は減りません。 - 在庫(棚卸資産):
50万円分の商品を仕入れても(現金減少)、それが売れるまではP/L上の「費用(売上原価)」になりません。現金は減っているのに、利益は減らないのです。 - 減価償却費:
P/Lでは「費用」として利益を減らしますが、実際には現金が出ていかない(過去に支払済み)費用です。
これらの「ズレ」を無視して利益だけを追うと、「利益は出ているのに、現金がない」という危険な状態に陥るのです。
【実践】資金繰り表の作り方(未来予測編)
資金繰り表に決まったフォーマットはありませんが、実務ではExcelやスプレッドシートで管理するのが一般的です。ここでは最もシンプルで強力な作り方を解説します。
必要なものと基本構成
まず、以下の資料を手元に用意してください。これらがないと「予測」ができません。
- 直近の試算表(P/LとB/S)
- 預金通帳(現在の現金残高の確認)
- 直近の総勘定元帳(B/S)
- 借入金返済予定表(銀行からの借入がある場合)
- 売掛金管理表(得意先ごとの入金予定日)
- 買掛金管理表(仕入先ごとの支払予定日)
- 固定費のわかるもの(家賃、リース料、給与台帳など)
基本構成は非常にシンプルです。
- 前月繰越(月初にいくら現金があったか)
- 経常収支(本業での入出金)
- 収入(売掛金回収、現金売上など)
- 支出(買掛金支払、人件費、家賃、その他経費、支払利息、税金など)
- 財務収支(借入・返済など)
- 収入(銀行からの借入、増資など)
- 支出(借入金の返済、配当金支払など)
- 設備収支(設備の購入・売却)
- 翌月繰越(月末にいくら現金が残るか)
( 1.前月繰越 + 2.経常収支+ 3.財務収支= 5.翌月繰越)+
試算表(P/L, B/S)から「予測」を作る方法
ここが実務のキモです。P/Lの「売上高」をそのまま資金繰り表の「収入」に書いてはいけません。必ず「入金日」ベースで考える必要があります。
(例:8月実績をもとに、9月・10月の資金繰り表を作る場合)
- 収入の予測
- **8月の試算表(B/S)**の「売掛金:500万円」を確認します。
- この500万円の入金予定日を「売掛金管理表」で確認します。
(例:A社 300万 → 9月末入金、B社 200万 → 10月末入金) - 資金繰り表の9月「収入」に300万、10月「収入」に200万と記載します。
- ※9月の「売上予測」も立て、その入金予定日(例:11月)も転記していきます。
- 支出の予測
- **8月の試算表(B/S)**の「買掛金:200万円」を確認します。
- この200万円の支払予定日を「買掛金管理表」で確認します。
(例:C社 200万 → 9月25日支払) - 資金繰り表の9月「支出」に200万と記載します。
- 「人件費」「家賃」などの固定費は、毎月ほぼ同額が発生します。実績に基づき9月、10月に転記します。
無料テンプレートで今すぐ始める
言葉で説明するより、実際に触っていただくのが一番です。シンプルなExcel / Googleスプレッドシートのテンプレートをご用意しました。まずはこれに自社の数字を当てはめてみてください。
シンプルな資金繰り表テンプレート(Excel/Spreadsheet)無料ダウンロード
資金繰り表(予算)作成の3つのコツ
私はクライアントに、予測を立てる際は以下の3点を徹底するようアドバイスしています。
- コツ1 : 予算は厳しめに(悲観的に)
- 「入金は遅く、出金は早く」見積もるのが鉄則です。
(例:9月末入金予定の売掛金は、10月上旬にズレる前提で計画する。支払いは必ず予定通りに出ていく前提で組む。)
- 「入金は遅く、出金は早く」見積もるのが鉄則です。
- コツ2 : 頻繁に振り返る、修正する(実績の反映)
- 資金繰り表は「作って終わり」ではありません。週に一度、最低でも月に一度は実績を反映し、予測を修正します。「予測と実績のズレ」を分析することが経営の精度を上げます。
- コツ3 : 「いつ」資金が底を突くか(最低残高)を監視する
- 月末残高がプラスでも、月中の「25日(給与・支払日)」に一時的にマイナスになる(=資金ショートする)ことがあります。残高が最も少なくなる日を常に監視してください。
【実践】キャッシュフロー計算書(C/S)の作り方(過去分析編)
C/Sは過去の分析ですが、これなくして未来の予測(資金繰り表)の精度は上がりません。中小企業こそ、過去の資金繰り(現預金の増減)の分析、「過去の診断」が必要です。
必要なもの:前期と当期のB/S、当期のP/L
C/Sは、B/S(貸借対照表)とP/L(損益計算書)の数字をパズルのように組み替えて作成します。そのため、2期分(前期末と当期末)のB/Sと、当期のP/Lが必要です。
「間接法」と「直接法」どちらを選ぶべき?
C/Sの作り方には、「直接法」と「間接法」という2つの考え方がありますが、難しく考える必要はありません。
- 結論:中小企業は「間接法」で十分です。
- 理由: P/Lの「利益」からスタートして、B/Sの増減を加減算するだけで作成でき、実務的な負担が少ないためです。上場企業の多くも間接法を採用しています。
C/Sの3つの区分(お金の流れの正体)
C/Sは、会社の活動を以下の3つに分けて現金の増減を示します。
- 営業活動によるキャッシュフロー(本業で稼ぐ力)
- 商品やサービスの販売、仕入、経費の支払いなど、本業から生じた現金の増減です。
- ここがプラスであることが絶対条件です。マイナスの場合、「本業で現金を生み出せていない」という重篤な状態です。
- 投資活動によるキャッシュフロー(未来への投資)
- 設備投資(機械の購入)、固定資産の売却、有価証券の売買など、未来のためにいくら投資し、いくら回収したかを示します。
- 成長企業は、設備投資でマイナスになることが多いです。逆に、資産売却でプラスになることもあります。
- 財務活動によるキャッシュフロー(資金調達と返済)
- 銀行からの借入(プラス)や返済(マイナス)、増資(プラス)など、資金調達に関する現金の動きです。
【図解イメージ】間接法の簡単な作り方ステップ
間接法は「利益」と「現金」のズレを調整していく作業です。
- Step1: P/Lの「税引前当期純利益」からスタート
- まず、P/Lの一番下にある「利益」をスタート地点に置きます。
- Step2 : 「現金支出のない費用」(減価償却費)を足し戻す
- 「減価償却費」はP/Lで費用になっていますが、実際には現金が出ていっていません。
- そのため、利益に足し戻します。(利益が過小評価されているため)
- Step3 : 「B/S項目」の増減を調整(※ここが最重要)
- 利益と現金のズレの元凶であるB/S項目を調整します。
- (例)売掛金が100万「増えた」
- → 利益は出ているのに、現金は未回収(入金していない)状態です。
- → 利益からマイナス100万します。
- (例)在庫(棚卸資産)が50万「増えた」
- → 仕入で現金が出ていった(または支払義務が増えた)のに、P/Lの費用になっていません。
- → 利益からマイナス50万します。
- (例)買掛金が30万「増えた」
- → 仕入れたが、まだ支払いを待ってもらっている(現金が出ていっていない)状態です。
- → 利益にプラス30万します。
この3ステップで計算されたものが「営業活動によるキャッシュフロー」の合計値になります。
最重要指標「フリーキャッシュフロー」とは?
専門的な話になりますが、これだけは覚えてください。
フリーキャッシュフロー(FCF) = 営業C/F + 投資C/F
これは、
「会社が本業で稼いだ現金から、未来への投資額を引いて、最終的に自由に使える現金がいくら残ったか」を示す数値です。
このFCFがプラスであれば、会社は借入に頼らずとも事業を回し、成長投資ができている健全な状態と言えます。銀行や投資家は、このFCFを最重要視します。
【応用】C/Sと資金繰り表を「連携」させて経営に活かす方法
競合記事の多くは「違い」の説明で終わっていますが、実務では「2つを連携させる」ことこそが最も重要です。
天気予報(資金繰り表)だけを見ていても、なぜ雨が降りやすい体質(C/S)なのかは分かりません。健康診断(C/S)だけを受けても、明日倒れないための行動(資金繰り表)には繋がりません。
「診断(C/S)なくして、精度の高い予測(資金繰り表)なし」です。
診断(C/S)なくして、予測(資金繰り表)なし
私がコンサルティングの場で必ず行うのが、この「連携」です。
(クライアント事例:製造業A社)
A社は常に資金繰りに追われていました。社長は「売上は伸びているのに、なぜだ」と悩んでいました。 そこで過去のC/Sを作成・分析(診断)したところ、「営業C/F」が利益を大幅に下回っていました。原因は「在庫(棚卸資産)の急増」だと分かりました。
売上増に備えて部品を大量に仕入れた結果、現金が在庫に変わり(キャッシュアウト)、資金繰りを圧迫していたのです。
活用例1:C/Sで「売掛金回収が遅い」と判明
- 診断(C/S):営業C/Fを分析した結果、「売掛金の増加」が突出して現金を圧迫していると判明。
- 行動(資金繰り表):
- まず、資金繰り表の「入金予測」を全体的に厳しく(遅めに)修正し、短期の資金ショートリスクに備えます。
- 同時に、営業部門と連携し、「入金サイトの交渉」や「回収遅延先への督促強化」という具体的な経営アクションに繋げます。
活用例2:C/Sで「営業C/Fがマイナス」と判明
- 診断(C/S):本業で現金を生み出せていない(赤字、または在庫・売掛金が異常)と判明。
- 行動(資金繰り表):
- 資金繰り表で、「あと何か月で現金が尽きるか」を即座にシミュレーションします。
- 資金が尽きる前(最低でも3ヶ月前)に、銀行にC/Sと改善計画書を持参し、「財務活動(借入)」の準備を始めます。
- 営業キャッシュフローをプラスにするために、P/Lの改善に着手します。
健全な経営のC/Sパターン6選
C/Sの3区分のプラス(+)/マイナス(-)の組み合わせで、会社の健康状態がわかります。
- ① 健全型(+/ - / -)
- 営業C/F:+(本業で稼げている)
- 投資C/F:-(未来へ投資している)
- 財務C/S:-(借金を返済できている)
→ 最も理想的な優良企業の形です。
- ② 成長投資型(+/ - / +)
- 営業C/F:+(本業で稼げている)
- 投資C/F:-(本業の稼ぎ以上に、積極的に投資している)
- 財務C/S:+(投資資金を銀行から調達している)
→ 事業拡大期の健全な姿です。
- ③ 危険水域型(- / + / +)
- 営業C/F:-(本業で現金を生めていない)
- 投資C/F:+(資産を売却して現金を作っている)
- 財務C/S:+(借入で運転資金を補填している)
→ **要注意** 資産売却や借入で延命している状態です。早急な営業C/Fの改善が必要です。
資金繰りとC/Sに関するよくある質問(FAQ)
Q1: 資金繰り表はどれくらいの頻度で作るべきですか?
A1: 月次(月間)の資金繰り表は必須です。 ただし、月中で資金ショートの可能性が発生しそうな場合、資金状況が厳しい(例:売掛金の入金サイトが長く、買掛金の支払サイトが短い)業界や、急速に成長している企業は、週次(週間)、さらには、日次(日繰り表)での管理を強く推奨します。
Q2: C/Sは中小企業でも作成義務がありますか?
A2: 法的な作成義務は上場企業のみです。 しかし、作成しないと「なぜ自社にお金がないのか」が永遠に不明なままです。また、銀行融資の審査では、P/LやB/Sと同じくC/Sの提出を求められることが常識化しています。自社の健康診断と銀行対策のためにも、必ず作成すべきです。
資金繰りが厳しいと相談いただいた企業は、ほとんどの場合、資金繰り表がない、キャッシュフロー計算書もない、という状態でした
Q3: 会計ソフトを使えば自動で作成できますか?
A3: C/S(過去の分析)は、多くの会計ソフトが対応しています。 ただし、資金繰り表(未来予測)は、会計ソフトでは作れません。なぜなら、未来の売上予測や入金予定は、社長や経理担当者の「予測」でしか入力できないからです。実務では「会計ソフトの実績」と「Excelなどの予測」を組み合わせて使います。
Q4: 資金繰り表とC/S、どちらが重要ですか?
A4: どちらも重要ですが、役割が違います。 「明日、会社を倒産させない」という短期的な守りのためには「資金繰り表」が最重要です。 「儲かる(現金が残る)会社に体質改善する」という長期的な攻めのためには「C/S」が最重要です。
Q5: 作成を税理士やコンサルタントに依頼するメリットは?
A5: 作成を代行してもらえる(時間の節約)のはもちろんですが、最大のメリットは「分析」と「改善策の提案」までサポートしてもらえる点です。
「営業C/Fが悪いので、在庫管理の方法を見直しましょう」「投資C/Fが過大なので、設備投資の優先順位を決めましょう」「財務C/Fを改善するため、銀行と金利交渉をしましょう」といった、具体的なアクションプランまで提示できるのが専門家の価値です。
まとめ:未来の「資金繰り表」と過去の「C/S」を両輪で回そう
「利益」だけを追う経営は、経営者として、事業継続のための必要な仕事を放棄していることになります。経営者の最大の使命は、事業を継続させることです
まずは、未来の天気予報である「資金繰り表」を作成し、短期的な倒産リスクを回避してください。 そして、過去の健康診断書である「キャッシュフロー計算書」で、なぜお金が残らないのか、体質的な原因を突き止めてください。
この2つを両輪で回し、「予測」と「分析」を繰り返すことこそが、「黒字倒産」の恐怖から解放され、本当に現金が残る強い会社を作る唯一の方法です。