
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
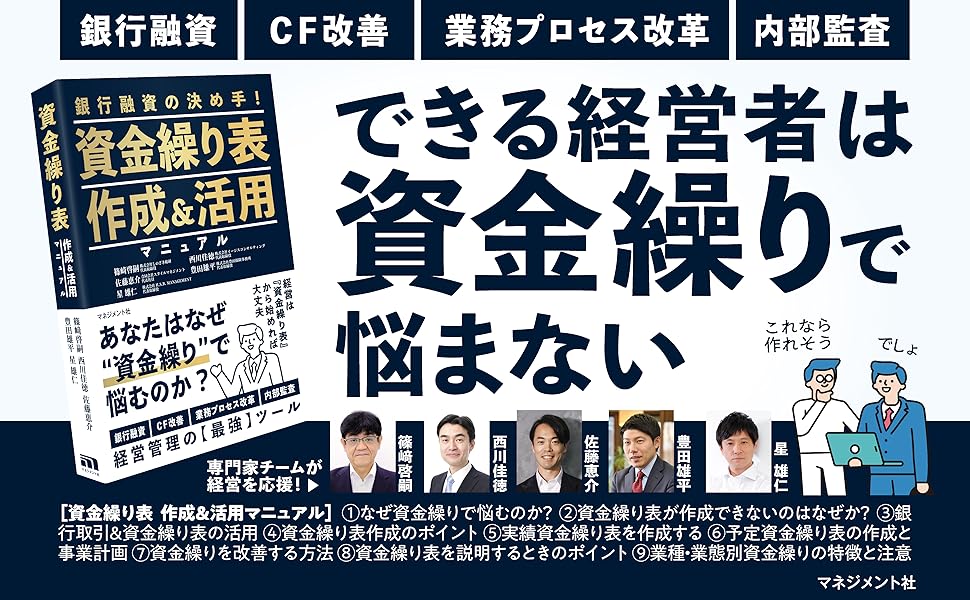
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
2026年5月25日、日本の金融界に大きな変革をもたらす可能性のある新しい制度「企業価値担保権(きぎょうかちたんぽけん)」が施行されます。
これは、一言で言えば**「会社の”将来性”そのものを担保にして融資を受ける」**ための仕組みです。
これまで「融資を受けたいが、担保になる不動産がない」「経営者である自分が個人保証(連帯保証)をしなければならない」といった悩みを抱えていた経営者にとって、これは待望の制度かもしれません。
しかし、新しい制度には必ずメリットと、まだ見えないリスクが伴います。
本記事では、長年多くの企業の資金繰りを支援してきた財務コンサルタントの視点から、この「企業価値担保権」とは何なのか、経営者として何を理解し、どう備えるべきかを、専門用語を極力使わずに解説します。

企業価値担保権とは?「事業の将来性」を担保にする新しい融資制度
企業価値担保権とは、2024年6月に成立した「事業性融資推進法」によって創設される、全く新しいタイプの担保権です。
施行は、2026年(令和8年)5月25日が予定されています。
この制度の最大の特徴は、「事業全体」を一つの担保パッケージとして扱える点にあります。
従来の担保は、
- 「この土地(不動産)」
- 「この機械(動産)」
- 「この売掛金(債権)」
といったように、個別の資産を指定する必要がありました。これを「個別資産担保」と呼びます。
しかし、企業価値担保権は違います。
土地や機械といった「目に見える資産(有形資産)」だけでなく、
技術力、ブランド、顧客基盤、ノウハウといった「目に見えない資産(無形資産)」も含めた「事業そのもの」の価値を評価し、丸ごと担保に入れることができます。
これにより、不動産を持たないスタートアップや、無形資産こそが価値の源泉であるIT企業、サービス業なども、事業の将来性を評価されれば大型の融資を受けられる可能性が出てきたのです。
なぜ今、企業価値担保権が必要とされたのか?(従来の課題)
なぜ今、このような新しい制度が国(金融庁)主導で進められたのでしょうか。
それは、私が現場で日々感じている、日本の金融における2つの大きな課題と直結しています。
課題1:不動産担保・経営者保証への過度な依存
日本の金融機関の融資審査は、長らく「いざという時に回収できるか」という視点、つまり「担保があるか」に重きが置かれてきました。
私が支援したあるIT企業(A社)は、画期的なソフトウェアを開発し、大手企業との取引も始まりかけていました。しかし、A社はオフィスを賃貸しており、担保となる不動産はありません。金融機関に融資を申し込んでも、「担保がない」「実績がまだ薄い」として、希望額の1割程度しか融資が下りませんでした。
結局、社長が個人資産を切り崩し、消費者金融からも借り入れて(経営者保証)、なんとか事業を継続しましたが、これは非常に危険な「タコ足経営」です。
このように、将来性(=企業価値)があるにもかかわらず、有形資産がないために資金調達できないというミスマッチが、日本の成長産業の足かせとなっていました。
課題2:金融機関の「伴走支援」の欠如
もう一つの課題は、金融機関が「担保を取って終わり」になりがちな点です。
不動産という確実な担保さえあれば、金融機関は「最悪、競売にかければ回収できる」と考え、その会社の経営状況や将来性に深く関与する動機が薄れがちでした。
これでは、金融機関は単なる「金貸し」であり、企業の成長を支える「パートナー」にはなれません。
企業価値担保権は、金融機関に「不動産ではなく、事業の将来性に目を向けなさい」と促す制度です。
事業全体を担保に取るということは、金融機関も「その事業が成長し続けないと、担保価値が下がり、融資が回収できなくなる」というリスクを企業と共有することになります。
これにより、金融機関側にも「企業価値を高めるために、積極的に経営支援(=伴走支援)をしよう」というインセンティブが働くことが期待されています。
企業価値担保権の3つの主要なメリット(期待される効果)
この新制度が施行されると、経営者には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。現時点で期待される3つの大きなメリットを解説します。
メリット1:無形資産・将来性が評価され、資金調達しやすくなる
これが最大のメリットです。
例えば、以下のような企業が融資を受けやすくなると期待されます。
- スタートアップ・IT企業: 高い技術力、特許、独自のアルゴリズム、獲得した顧客基盤(サブスクリプションの契約数など)を評価される。
- サービス業・ブランド企業: 強力なブランド力、独自の接客ノウハウ、フランチャイズ網などを評価される。
- 研究開発型企業: すぐには売上にならなくとも、将来有望な研究開発(R&D)の進捗を評価される。
これまで「うちは担保がないから」と諦めていた企業にも、新たな資金調達の道が開かれます。
メリット2:経営者保証が不要になる(可能性が高い)
日本の廃業理由の一つに、「後継者不足」があります。その背景には、後継者が「会社の借金の個人保証を引き継ぎたくない」という問題があります。
企業価値担保権は、「会社全体」を担保に入れる制度です。事業の価値が融資額を十分上回っていると評価されれば、経営者個人が保証する必要性が大きく低下します。
これにより、経営者は個人資産と会社の経営を切り離す「公私分離」が実現しやすくなり、思い切った事業展開や、スムーズな事業承継(M&A含む)に繋がることが期待されます。
【専門家の視点】「ゼロゼロ融資」後の経営者保証問題
コロナ禍の「ゼロゼロ融資」で、多くの中小企業が実質無利子・無担保で融資を受けましたが、その多くで経営者保証は残っています。返済が本格化する中、この個人保証が重荷になっている経営者は少なくありません。企業価値担保権は、こうした既存の借入を借り換える際、経営者保証を外す交渉カードとしても使える可能性があります。
メリット3:金融機関による「伴走支援」が期待できる
前述の通り、金融機関は「貸したお金が返ってくるか」を常に見ています。
企業価値担保権では、その「担保」=「事業の価値」そのものです。
もし企業の業績が悪化すれば、担保価値も下がります。
そのため、金融機関は「業績が悪化しそうだ」と分かった時点で、放置するのではなく、「どうすれば企業価値(業績)を維持・向上できるか」を経営者と一緒になって考える動機が生まれます。
- 販路拡大のビジネスマッチング
- コスト削減のコンサルティング
- DX(デジタル化)の支援
こうした「伴走支援」が、従来の担保融資よりも手厚くなることが期待されます。
注意すべき課題とデメリット(想定されるリスク)
もちろん、良いことばかりではありません。新制度は未施行であり、実際に運用が始まると「こんなはずではなかった」という問題が出てくる可能性があります。
財務コンサルタントとして、現時点で懸念される4つの課題・デメリットを指摘します。
課題1:商業登記簿への記載による「信用不安」の懸念
企業価値担保権を設定すると、その事実は会社の「商業登記簿(登記簿謄本)」に記載されます。
登記簿は誰でも取得できるため、取引先があなたの会社の登記簿を見たときに、「企業価値担保権設定」という見慣れない記載を見つけることになります。
これにより、取引先が「この会社は、事業全体を担保に入れないと融資が受けられないほど経営が苦しいのではないか?」と誤解し、信用不安につながるリスクが指摘されています。
(※ただし、これは制度が普及すれば解消される「初期の課題」である可能性もあります)
課題2:制度の「濫用防止」による利用制約の可能性
この制度は強力な分、「既存の債権者(銀行など)を害する」ような使われ方(=濫用)が懸念されています。
そのため、法律では「誰でも自由に使える」わけではなく、一定の制約が課される見込みです。
例えば、「設定できる金融機関は限定される」「一定の財務基準を満たす必要がある」といった条件が付く可能性があります。スタートアップが自由に使えるようになるまでには、金融機関側の体制整備も含め、時間がかかるかもしれません。
課題3(推定):信託コストの発生
企業価値担保権のスキーム(後述)では、多くの場合「信託会社」が関与します。
金融機関(貸し手)と企業(借り手)の間に、中立的な立場で担保(事業価値)を管理する役割です。
これは透明性を高めるメリットがある一方、企業側は金融機関への利息とは別に、**信託会社への「信託報酬(手数料)」**を支払う必要が出てくると想定されます。
このコストが、従来の担保融資の保証料などと比べて割高になる可能性は否定できません。
課題4(推定):経営の自由度への影響
事業「全体」を担保に入れるということは、裏を返せば、経営における重要な判断に金融機関や信託会社の「目」が入ることを意味します。
例えば、
- 大規模な設備投資
- 新規事業への進出
- 不採算部門の売却といった「企業価値に大きな影響を与える経営判断」を行う際に、事前に金融機関への報告や、場合によっては承諾が必要になる可能性があります。
経営者にとっては、「経営の自由度が低下した」と感じる場面が出てくるかもしれません。
企業価値担保権の仕組み(スキーム)
少し専門的になりますが、この制度が「なぜ機能するのか」の仕組みを解説します。
この制度では、多くの場合、以下の三者が登場します。
- 債務者(企業):融資を受ける会社
- 貸し手(金融機関):融資を行う銀行など
- 担保権者(信託会社など):担保(事業価値)を管理する中立な存在
なぜ、間に「信託会社」が入るのでしょうか?
これは、事業価値という「目に見えないもの」を公平に評価・管理するためです。
もし貸し手(金融機関)が担保権者も兼ねてしまうと、自社に都合の良いように担保価値を評価したり、過度に経営に介入したりする恐れがあります。
そこで、中立的な第三者である信託会社が「担保権者」として間に入ることで、公平な運用を目指す仕組みが想定されています。(※信託を使わないパターンも想定されていますが、これが主流になると見られています)
企業価値担保権の利用手続き(想定フロー)
では、2026年5月の施行後、経営者は具体的に何をすればよいのでしょうか。
現時点での「想定フロー」をステップバイステップで解説します。
【注意】
あくまで施行前の「想定」です。実際の運用は金融機関ごとに異なる可能性があります。
ステップ1:金融機関への相談と「事業性評価」の依頼
まずは取引のある金融機関、あるいはスタートアップ支援に強い金融機関に、「企業価値担保権を活用した融資」について相談します。
この時、最も重要なのが「事業性評価」です。
あなたの会社の「無形資産(技術、ブランド、顧客基盤など)」がどれだけの価値を持つのかを、金融機関に説明するための資料(事業計画書、知財リスト、顧客データ分析など)を準備する必要があります。
ステップ2:金融機関による審査・信託会社の選定
金融機関は提出された資料を基に、事業の将来性やリスクを審査します。
融資可能と判断されれば、スキーム(信託を使うか等)を決定し、必要に応じて信託会社が選定されます。
ステップ3:信託契約・担保権設定契約の締結
企業、金融機関、信託会社の三者(または二者)で、信託契約や担保権設定契約を締結します。
ここで、「どの範囲の事業を担保とするか」「経営上の報告義務」などの詳細が決定されます。
ステップ4:担保権設定と登記
契約に基づき、法務局で「企業価値担保権設定」の登記手続きを行います。(※この時点で登記簿に記載されます)
ステップ5:融資実行
登記が完了し、すべての手続きが終わると、金融機関から融資が実行されます。
ステップ6:定期的なモニタリング(伴走支援)
融資実行後も、契約に基づき、定期的に(例:四半期ごと)業績や事業の状況を金融機関や信託会社に報告します。金融機関は、この報告に基づき、必要な伴走支援を提供します。
既存の担保(不動産・ABL・経営者保証)との違い(比較表)
最後に、この新制度が、従来の方法とどう違うのかを表で整理します。
特に、すでにある「ABL(動産・債権担保融資)」との違いが分かりにくいかもしれませんが、ABLが「個別の在庫や売掛金」を対象にするのに対し、企業価値担保権は「事業全体(無形資産含む)」を対象にする点で大きく異なります。
| 比較項目 | 企業価値担保権 (新制度) | 不動産担保 (従来) | ABL (動産・債権担保) | 経営者保証 (従来) |
| 担保対象 | 事業全体(有形・無形資産) | 土地・建物 | 在庫・売掛金・機械設備 | 経営者個人の全資産 |
| 評価の軸 | 事業の将来性・収益性 | 資産の時価(換金価値) | 資産の時価(換金価値) | 経営者の個人資産・信用力 |
| 経営への関与 | 強い(伴走支援が前提) | 弱い(返済が滞るまで) | 中程度(在庫等の管理) | 非常に強い(実質一体) |
| 登記 | 必要(商業登記簿) | 必要(不動産登記簿) | 必要(債権譲渡登記など) | 不要 |
| 主なメリット | 無形資産を評価、経営者保証の脱却 | 低金利・長期の融資 | 不動産が無くてもOK | (金融機関側のメリット大) |
| 主なデメリット | コスト、経営自由度の低下懸念 | 不動産が必要 | 担保価値の変動、管理コスト | 経営者のリスク無限大 |
結論:企業価値担保権の活用を検討すべき企業とは
企業価値担保権は、多くの経営者にとって「武器」となり得る制度です。
特に、以下のような企業は、2026年の施行に向けて今から情報収集と準備(事業計画のブラッシュアップ)を進めるべきです。
- 高い技術力やブランド、顧客基盤を持つが、不動産担保に乏しい企業(例:IT、SaaS、コンテンツ制作、研究開発型企業)
- 経営者保証を外したい、または事業承継をスムーズに進めたい企業(例:後継者に個人保証を引き継がせたくないオーナー経営者)
- 金融機関からの積極的な経営支援(伴走支援)を希望する企業(例:自社の弱みを補完してくれるパートナーとして金融機関と付き合いたい企業)
この制度は、単に「お金を借りる」ためのものではなく、「自社の真の価値(将来性)を金融機関に認めさせ、パートナーとして共に成長する」ための新しい選択肢です。
企業価値担保権に関するFAQ(よくある質問)
Q. 企業価値担保権はいつから利用できますか?
A. 2026年(令和8年)5月25日から施行・利用可能になる予定です。
Q. 企業価値担保権を使えば、必ず経営者保証は外せますか?
A. 制度の目的は経営者保証への依存を減らすことですが、必ず外せるとは限りません。金融機関が「事業価値だけではリスクをカバーできない」と判断した場合、一部の保証を求められる可能性は残ります。
Q. 赤字の企業でも利用できますか?
A. 可能性があります。 従来の不動産担保と異なり、「事業の将来性」が評価軸です。現時点で赤字でも、将来的な成長性(技術力、市場シェア、優秀な人材など)が評価されれば、利用できる可能性があります。
Q. 担保に設定すると、登記簿に載ってしまうのですか?
A. はい、その見込みです。 担保権を設定した旨が商業登記簿に記載されます。これが取引先の信用不安を招く懸念(課題)も指摘されています。
Q. 費用(コスト)はどれくらいかかりますか?
A. 制度が未施行のため詳細は未定ですが、融資利息のほかに、信託会社を利用する場合は**「信託報酬」が、また登記手続きのための「登録免許税」**などが発生すると想定されます。
企業価値担保権は、日本の資金調達のあり方を大きく変える可能性を秘めています。
しかし、その恩恵を最大限に受けるためには、「自社の強み(無形資産)は何か」を経営者自身が深く理解し、それを客観的なデータや言葉で金融機関に説明できる準備が必要です。
施行までまだ時間はあります。まずはご自身の会社の「目に見えない価値」を棚卸しすることから始めてみてはいかがでしょうか。