
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
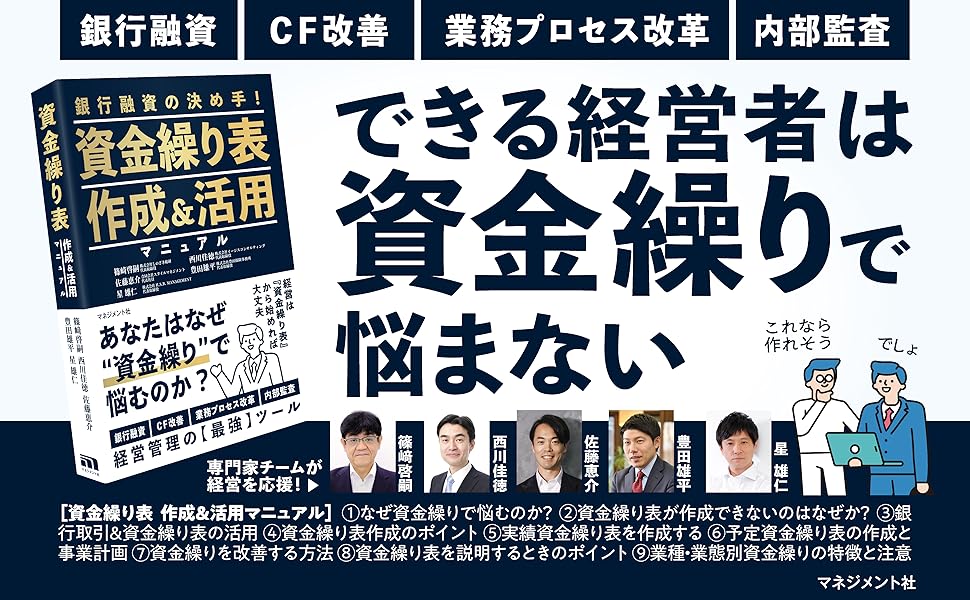
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
銀行融資を申し込む際、必ず提出する決算書。
多くの経営者が「今期は黒字になった(P/L)」「売上が伸びた」という点をアピールしようとされます。
しかし、私たち財務コンサルタントが銀行員と折衝する際、彼らが最重要視しているのはそこではありません。
銀行が本当に知りたいのは、
「貸した金を確実に返せるか(返済能力)」
「貸したお金を何に使うか(資金使途)」
「万が一の時に回収できるか(担保力)」
といった点です。
そのシビアな視点で、彼らはP/L(損益計算書)よりもB/S(貸借対照表)を、それも帳簿の数字そのままではなく実質的な「実態」で評価します。
この記事では、融資の現場で数々の企業の資金繰りを改善してきた専門家の視点から、銀行員の「本音」の視点と、融資評価を格段に上げるための具体的な対策を徹底的に解説します。

結論:銀行は決算書を「実態」でしか評価しない
銀行員が決算書を受け取って最初に行う作業は、経営者や税理士が作成した決算書を「銀行目線」の決算書に修正することです。
財務分析の世界では、これを「実態貸借対照表(じったいたいしゃくたいしょうひょう)」への修正と呼びます。これは、銀行の融資審査における「常識」です。
銀行はなぜP/L(利益)を信用しないのか?
多くの経営者が「利益さえ出ていれば銀行は貸してくれる」と誤解されていますが、銀行はP/L(損益計算書)の数字を鵜呑みにしません。
理由は3つあります。
- 利益は操作が容易(粉飾)だから
銀行員は、粉飾決算の典型的な手口を熟知しています。例えば、「期末に在庫を水増しする」「翌期の売上を前倒しで計上する」といった操作で、利益は簡単にかさ上げできます。彼らはそうした「作られた利益」をすぐに見抜きます。 - 節税と融資のジレンマを理解しているから
中小企業は「税務署向け(節税=赤字にしたい)」と「銀行向け(融資=黒字にしたい)」という矛盾した要求に常にさらされています。銀行はその実情を理解しており、提出された黒字決算が「融資向け」に調整されたものでないか、常に疑いの目を持っています。 - 利益と現金(キャッシュ)は別物だから
これが最も重要です。「勘定合って銭足らず」という言葉通り、帳簿上でどれだけ利益が出ていても、手元の現金が尽きれば会社は倒産します(黒字倒産)。銀行が貸すのは「現金」であり、返済してもらうのも「現金」です。利益の数字ではなく、実際の「現金(キャッシュ)を生み出す力」こそが評価対象なのです。
銀行の「実態」評価とは?
銀行の「実態」評価とは、
一言で言えば「資産から“価値のないもの”を差し引く」という作業です。
銀行はB/S(貸借対照表)の「資産の部」を精査し、以下の項目を「実質ゼロ」として評価し直します。
この修正作業の結果、多くの企業で恐ろしいことが起こります。 帳簿上は資産が1億円、負債が9,000万円で「純資産1,000万円(黒字)」だったとしても、銀行の実態評価で「価値のない資産」が1,500万円認定されると、実態は「純資産マイナス500万円」となります。
- 回収不能な売掛金: 何年も回収できていない売掛先は残っていませんか?
- 売れない在庫(不良在庫): 長期間動いていない在庫、流行遅れの商品は資産ではありません。
- 使途不明な仮払金・貸付金: 社長への貸付金や、中身が不明瞭な仮払金は「社外流出」とみなされます。
- 有形固定資産: 減価償却の過不足はないか。事業性の資産は簿価(取得時)による評価、遊休資産は時価(今現在の売却価格)による評価
- 投資有価証券: 売却時の、売却益もしくは売却損を加味する
これが「実質債務超過」です。
経営者本人は黒字だと思っていても、銀行の評価は「実質破綻懸念先」。これでは新規融資が通らないのも当然です。
銀行が見る3つの決算書と「最重要」書類
銀行に融資を申し込む際、一般的に以下の4点セットの提出を求められます。
- 貸借対照表 (B/S): 会社の財産状態(銀行にとって最重要)
- 損益計算書 (P/L): 会社の儲け
- 勘定科目内訳明細書: B/S, P/Lの「中身」(B/Sと同じくらい重要)
- 法人事業概況説明書(申告書別表): 税務署への申告書類
経営者や、失礼ながら多くの「節税専門」の税理士はP/Lを重視します。
しかし、融資担当の銀行員は違います。彼らが真っ先に、そして最も時間をかけて分析するのは「B/S」と「勘定科目内訳明細書」です。
B/Sで全体の数字を掴み、その「中身=実態」を勘定科目内訳明細書で徹底的に確認する。このセットで、会社の本当の姿は丸裸にされます。
【最重要】貸借対照表(B/S)で銀行が見る6つのポイント
では、具体的に銀行はB/Sのどこを見て「実態評価」を行っているのでしょうか。融資審査の現場で必ずチェックされる6つの最重要ポイントを解説します。
ポイント1:現金・預金(最優先)
銀行がB/Sの資産の部で最初に見る、そして最も重視する項目が「現金・預金」です。なぜなら、これが「返済原資そのもの」だからです。
- 目安は「平均月商の3ヶ月分」
資金繰りコンサルタントとして私たちが推奨し、多くの銀行員も「安心できるライン」と口を揃えるのが「平均月商の3ヶ月分」の現預金です。最低でも1.5ヶ月分は確保したいところです。 - 「見せ金」は即座にバレる
決算日だけ、どこかから短期で借り入れてきて預金残高を一時的に厚く見せる「見せ金」を行う経営者がいますが、これは逆効果です。銀行は「勘定科目内訳明細書」で期中の預金の動き(平均残高、通称:平残)や短期借入金の増減もチェックしています。「決算日だけ突出して残高が多い」ことはすぐにバレ、むしろ「資金繰りに窮している証拠」として心証を著しく悪化させます。
ポイント2:純資産(自己資本)
B/Sの右下にある「純資産の部」。これは「返済不要の、本当の自分の資本」です。この合計額がマイナスになっている状態を「債務超過」と呼びます。
債務超過は、銀行格付けにおいて「破綻懸念先」以下に分類される決定的な要因です。この状態では、原則として新規融資は停止され、既存融資の一括返済や担保の追加差し入れを求められることになります。
ただし、ここで一つ重要なポイントがあります。 純資産がマイナス(債務超過)でも、次の「役員借入金」が多額にあれば、銀行は「実質債務超過ではない」と判断してくれるケースが多いのです。
ポイント3:役員借入金・貸付金
B/Sには、社長個人と会社のお金の貸し借りが記録されています。この2つは、銀行評価において天国と地獄ほどの差があります。
- 役員借入金(プラス評価)
これは、社長が会社に貸しているお金です(負債の部に計上)。銀行はこれを「実質的な資本金」とみなし、プラス評価します。なぜなら、社長は会社が苦しい時にこの返済を要求しない(=返済不要の資本)と判断するからです。前述の通り、これが多ければ実質債務超過とはみなされません。 - 役員貸付金(マイナス評価)
これは、会社が社長に貸しているお金です(資産の部に計上)。これは銀行評価における「最大のがん」の一つです。銀行はこれを「使途不明金」「役員賞与の隠蔽(税務逃れ)」「会社の私物化」とみなし、資産価値ゼロ(=実態評価で全額控除)とします。
私が担当したある運送会社では、業績は悪くないのに融資が出ないと悩んでいました。B/Sを拝見すると、資産の部に多額の「役員貸付金」が。理由を尋ねると「社長個人の生活費や遊興費」でした。これでは銀行が「会社のお金を社長が横領している」と判断しても仕方ありません。この貸付金を解消(役員報酬との相殺など)するだけで、銀行の評価は劇的に改善しました。
ポイント4:売掛金・在庫(資産の「質」)
売掛金や在庫(棚卸資産)は、資産の部で大きな割合を占めることが多い項目です。銀行はこれらの「量」ではなく「質」を厳しくチェックします。
- 売掛金:
「勘定科目内訳明細書」で、売掛先ごとの残高と滞留期間を見ます。特定の取引先に依存しすぎていないか? 何ヶ月も回収できていない不良債権はないか? - 在庫(棚卸資産):
売上高と連動しているかを見ます。例えば、売上が横ばいなのに、在庫だけが前年比2倍に増えている場合、「不良在庫の山」か「利益を出すための粉飾」を疑います。
ポイント5:仮払金・貸付金(使途不明金)
前述の「役員貸付金」と同様に、中身が不明瞭な「仮払金」や「(役員以外への)貸付金」も、銀行は「使途不明金」として資産価値ゼロと評価します。
これらが多額に計上されていると、「この会社は経理処理がずさんだ」「融資したお金も、事業以外に流用されるのではないか」という疑念を持たれ、融資審査以前の「信用力」を失うことになります。
ポイント6:借入金月商倍率
これは、会社が「稼ぎ(月商)に対して、どれだけ借金をしているか」を見る指標です。
計算式: 借入金総額 ÷ 平均月商 = 借入金月商倍率
業種によって尺度は異なりますが、一般的な中小企業(製造業や卸売・小売業)の目安として、銀行は以下のように見ています。
- 3ヶ月以内: 健全な範囲。
- 3ヶ月~6ヶ月: やや多い。融資は慎重になる。
- 6ヶ月超: 過大債務。追加融資は非常に困難。
ただし、これはあくまで目安です。不動産賃貸業や、大型の設備投資を必要とする装置産業などでは、この倍率が高くなるのは当然です。
重要なのは、自社の業種特性を踏まえ、この倍率が過大になっていないか(=返済能力を超えた借入をしていないか)を常に意識することです。