
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
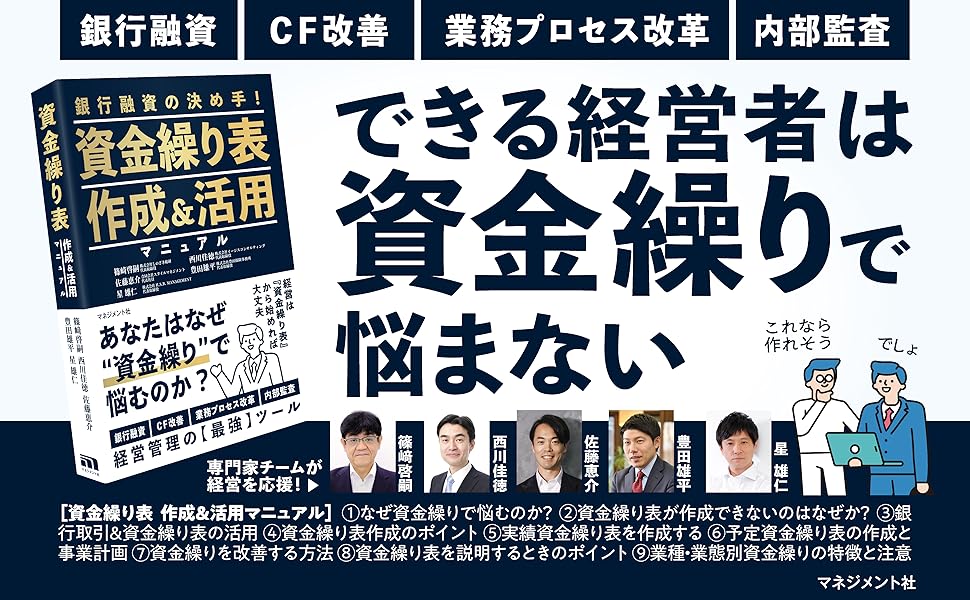
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「得意先からの入金が遅れてる…」その悩み、放置は危険です。
本記事では、入金遅延の原因特定から、丁寧な催促、法的手続き、そして未来の未回収を防ぐ予防策までを、実務に沿って徹底解説します。
【この記事でわかること】
- 得意先からの入金が遅れるよくある理由
- 角が立たない、効果的な催促メール・電話のテンプレート
- 入金遅延が続いた場合の段階的な対応フロー
- 未回収リスクを未然に防ぐための契約・与信管理のポイント
「いつも期日通りに入金してくれる得意先から、なぜか今回は入金がない」
「催促したいけれど、関係を悪化させたくない…」
企業の資金繰り・財務を見ていると、こうした売掛金の悩みは日常茶飯事です。
しかし、「そのうち払ってくれるだろう」という楽観視や、「催促しづらい」という遠慮は、自社の資金繰りを悪化させる命取りになりかねません。
長年のコンサルティング経験から断言できるのは、入金遅延は、その大小にかかわらず「事業のリスクシグナル」であるということです。
この記事では、数多くの企業の資金繰りを改善してきた専門家の視点から、入金遅延という問題にどう向き合い、どう解決していくべきかを具体的にお伝えします。
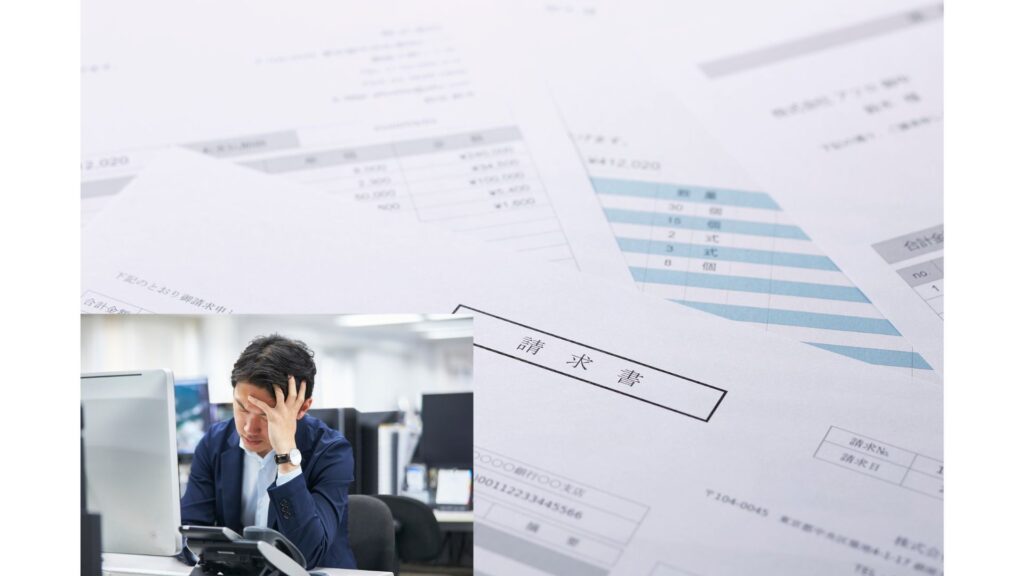
「入金が遅い」と感じたらまず確認すべき3つのこと
感情的に「どうして入金してくれないんだ!」と焦る前に、まずは冷静に自社の状況を確認しましょう。私の経験上、入金遅延の約3割は、請求側の単純なミスや認識違いが原因です。
【セルフチェックリスト】
これらの確認を怠って催促してしまうと、かえって自社の信用を損なうことになりかねません。まずは事実確認を徹底してください。
なぜ?得意先の入金が遅れる5つの主な理由
自社にミスがないことを確認できたら、次に入金が遅れる理由を探っていきましょう。原因によって、こちらの取るべき対応も変わってきます。
- 理由1:うっかりミス(経理担当者の失念、振込日間違い)
最も多いのがこのパターンです。特に、相手が中小企業で経理担当者が少ない場合や、月末の繁忙期に発生しがちです。悪意はないため、丁重に連絡すればすぐに対応してもらえることがほとんどです。 - 理由2:自社への不満(納品物へのクレームなど)
納品した商品やサービスに何らかの不満があり、支払いを保留にしているケースです。催促の連絡をした際に、「実は、先日の納品物に不具合があって…」といった反応があれば、まずはその問題解決を優先する必要があります。 - 理由3:先方の社内事情(担当者不在、承認プロセスの遅延)
請求書の承認フローが複雑だったり、決裁者が長期出張中だったりと、社内手続きが原因で支払いが遅れることもあります。特に、取引を始めたばかりの大企業でよく見られます。 - 理由4:資金繰りの悪化(キャッシュフローの一時的な問題)
これは注意が必要なサインです。「少し待ってほしい」「分割で支払わせてほしい」といった相談があった場合は、相手の資金繰りが悪化している可能性があります。一時的なものか、恒常的なものかを見極める必要があります。 - 理由5:倒産の兆候(危険なサインの見分け方)
最も深刻なケースです。これは単なる入金遅延ではなく、事業存続の危機が背景にある可能性があります。
【コンサルタントの視点:危険な兆候を見逃すな】 私が過去に見てきた倒産事例には、必ず前兆がありました。以下のようなサインが複数見られたら、最大限の警戒が必要です。
✔ 担当者と急に連絡が取れなくなる。(電話に出ない、メールの返信がない)
✔ 入金遅延の理由が二転三転する。(「経理が休みで…」→「システムトラブルで…」など)
✔ これまでなかった少額の取引でさえ、支払いが遅れる。
✔ オフィスに電話したら、すでに解約されていた
これらは危険度90%以上のシグナルです。悠長に構えている時間はありません。すぐに債権回収の準備に取り掛かるべきです。
【テンプレート付】角を立てずに催促する3ステップ
催促は、相手との関係性を維持しながら、こちらの要望を明確に伝える必要があります。感情的にならず、以下の3ステップで段階的に進めていきましょう。
ステップ1:メールでの確認(1〜3営業日遅延)
まずは、「お忘れではないでしょうか?」というスタンスで、柔らかく確認のメールを送ります。攻撃的な印象を与えないことが重要です。
件名:【株式会社〇〇】お振込みご確認のお願い(請求書番号:XXXXX)
株式会社△△ 経理ご担当者様
いつもお世話になっております。 株式会社〇〇の〇〇です。
〇月〇日付でご請求いたしました「(件名)」(請求書番号:XXXXX)につきまして、 本日〇月〇日時点で、ご入金の確認が取れておりませんでしたので、ご連絡いたしました。
誠に恐れ入りますが、ご状況はいかがでしょうか。 もし、本メールと行き違いでお振込みいただいておりましたら、何卒ご容赦ください。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。
【プロのコツ】 この段階では「催促」や「督促」という言葉は絶対に使わないでください。「ご確認のお願い」という表現に留めるのが、角を立てないポイントです。また、請求書番号や件名を具体的に記載することで、相手の確認作業を助ける配慮も大切です。
ステップ2:電話での確認(1週間以上の遅延)
メールに反応がない、あるいは「確認します」と言われたきり入金がない場合は、電話で直接確認します。メールよりも状況を詳しく聞ける利点があります。
<電話での会話スクリプト例>
あなた: 「いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。経理ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか?」
(担当者につないでもらう)
あなた: 「お忙しいところ恐れ入ります。先日メールでもご連絡いたしました、〇月〇日期日のお支払いについて、ご確認状況はいかがでしょうか?」
相手: 「あ、すみません、確認します…」
あなた: 「ありがとうございます。もし何かお手続き上でお困りの点などございましたら、お申し付けください。ちなみに、いつ頃お振込みいただけそうでしょうか?」
【プロのコツ】 最後の「いつ頃お振込みいただけそうでしょうか?」という一言が非常に重要です。これにより、相手に具体的な期日を意識させ、口約束でも言質を取ることができます。ここで曖昧な返事をされた場合は、理由4や5の可能性を疑い始めるべきです。
ステップ3:督促状の送付(2週間以上の遅延)
電話でも進展がない場合、書面での催促に切り替えます。これは、こちらの「正式な要求」であるという意思表示になります。
- 普通郵便での督促状: まずは通常郵便で送付し、記録を残します。
- 内容証明郵便での督促状: それでも反応がなければ、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる内容証明郵便を利用します。これは法的措置を視野に入れた最終通告であり、相手に強いプレッシャーを与えることができます。
督促状には、
請求内容、支払期日、振込先といった情報に加え、
「本書面到着後、〇日以内にお支払いいただけない場合、誠に不本意ながら法的手続きを検討せざるを得ません」といった一文を添えます。
それでも入金されない場合の法的措置とは
督促状を送っても支払いがない場合、いよいよ法的な手段を検討するフェーズに入ります。ここでは、中小企業でも比較的利用しやすい手続きを簡単にご紹介します。
- 支払督促: 裁判所を通じて相手に支払いを命じてもらう手続き。相手が異議を申し立てなければ、強制執行が可能になります。手続きが比較的簡単で費用も安いのが特徴です。
- 民事調停: 裁判所で調停委員を交えて、話し合いによる解決を目指す方法。円満な解決を望む場合に適しています。
- 少額訴訟: 60万円以下の金銭支払いを求める場合に利用できる、原則1回の期日で審理が終わる迅速な訴訟手続きです。
どの手続きを選ぶべきかは、債権額や相手の状況によって異なります。この段階になったら、いたずらに時間を浪費せず、速やかに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。初回相談を無料で行っている法律事務所も多いので、まずは情報収集から始めてみましょう。
今後の未回収リスクを防ぐ4つの予防策
問題が解決したら、それで終わりではありません。重要なのは、「なぜ今回の遅延が起きたのか」を分析し、未来のリスクを防ぐ仕組みを作ることです。これは、財務コンサルタントとして私が最も重視するポイントです。
【未回収リスク予防チェックリスト】
契約書に支払条件・遅延損害金を明記する
「支払いが遅れた場合は、年率〇%の遅延損害金を請求する」という一文があるだけで、強力な牽制になります。
(まとめ)入金遅延は迅速かつ冷静な対応が鍵
得意先からの入金遅延は、どんな企業にとっても悩ましい問題です。しかし、対応の流れを理解し、準備しておくことで、慌てずに対処することができます。
【対応フローのおさらい】
- 自社にミスがないか確認
- 原因を推測
- メール → 電話 → 書面 の順で段階的に催促
- 解決しない場合は専門家へ相談
- 再発防止策を講じる
最も重要なのは、問題を先送りにしないことです。入金遅延は、時間が経てば経つほど回収が困難になります。本記事を参考に、ぜひ迅速かつ冷静な第一歩を踏み出してください。
もし、貴社の資金繰りや与信管理体制に根本的な課題を感じているようでしたら、一度私たちのような外部の専門家にご相談いただくのも一つの手です。客観的な視点から、貴社に最適な解決策をご提案いたします。