
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
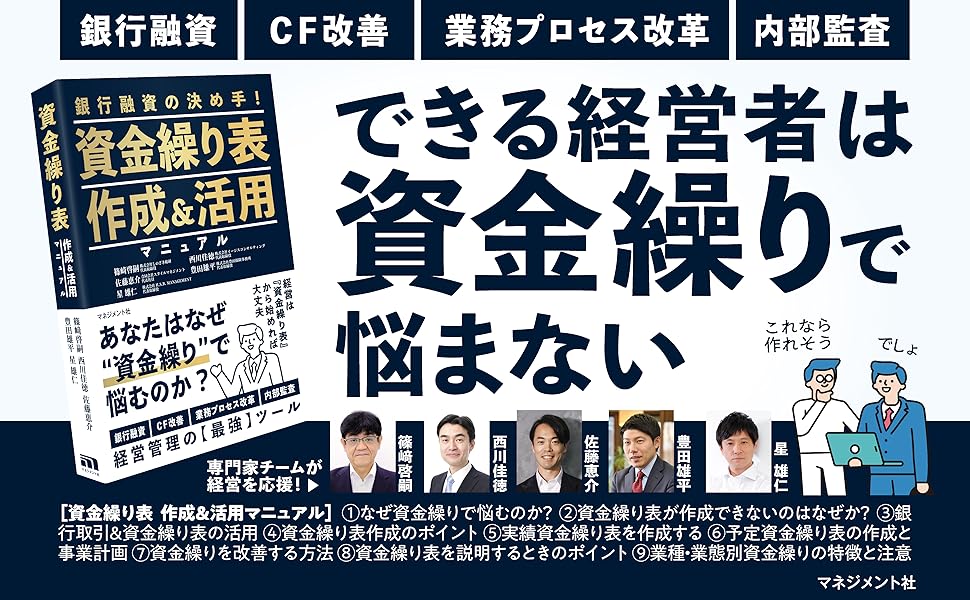
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「決算書では利益が出ているはずなのに、なぜか手元にお金が残らない…」
「売上は伸びているのに、支払日が近づくといつも不安になる…」
経営者であるあなたも、こんな悩みを抱えていませんか?その状態、放置すると非常に危険です。それは「黒字倒産」の黄色信号かもしれません。
この記事では、資金繰りのプロが、黒字なのにお金がなくなる5つの根本原因を徹底解剖し、明日からすぐに実践できる7つの具体的な対策を現場目線で分かりやすく解説します。

もしかして、あなたの会社も?「黒字倒産」危険度チェックリスト
まずは、ご自身の会社の状況を客観的に把握してみましょう。以下の10個の質問のうち、いくつ当てはまりますか?
- [ ] 月末の支払いのために、入金予定を常に気にしている
- [ ] 売掛金の回収が2ヶ月以上先になる取引先がある
- [ ] 売上が急に伸びて、仕入れや人件費の支払いが先に増えた
- [ ] 社長である自分が、会社の今後の現預金残高がどうなるか?を即答できない
- [ ] どんぶり勘定で「多分これくらい儲かっているだろう」と感覚で判断している
- [ ] 在庫の中身(何が・いくつあるか)を半年以上確認していない
- [ ] 新しい設備や大きな投資を、金融機関の提案だけで決めたことがある
- [ ] 税金や社会保険料の支払いを、期限ギリギリまで後回しにしがちだ
- [ ] 借入金の返済額が、毎月の利益の半分以上を占めている
- [ ] 「資金繰り表」を作成していない、または更新が止まっている
診断結果:
- 0〜2個: 健全な状態です。しかし、油断は禁物。この記事で知識を深め、予防策を徹底しましょう。
- 3〜5個: 黄色信号です。すでに資金繰りに課題を抱え始めています。原因を特定し、すぐに対策が必要です。
- 6個以上: 赤信号です。いつ資金ショートしてもおかしくない危険な状態です。一刻も早くこの記事を読み進めてください。
そもそも「黒字なのにお金がない」とはどういう状態?利益と現金のズレを理解する
なぜ「黒字」なのに「お金がない」という不思議な現象が起きるのでしょうか?
それは、会社の成績表である「損益計算書(PL)」で計算される利益と、実際に会社にある現預金(キャッシュ)の増減が、一致しないからです。
- 利益(会計上の儲け): 商品を販売した「時点」で計上される(発生主義)。お金がまだ入金されていなくても、売上としてカウントされます。
- 現金(手元のお金): 実際にお金が入金・出金された「時点」で増減する(現金主義)。
この「利益」と「現金」のタイムラグこそが、黒字倒産の根本的な原因です。
例えば、100万円の商品が売れた場合、会計上は即座に100万円の売上が立ちます。しかし、その代金が2ヶ月後に入金される契約なら、2ヶ月間は手元に1円も入ってきません。その間に仕入れ代金や給料の支払いが先に50万円あれば、100万円入金の前に会社のお金は50万円減ってしまうのです。
これが「黒字なのにお金がない」状態の正体です。
損益計算書だけを見て「利益が出ているから大丈夫」と安心していると、この現金の動きを見逃し、ある日突然、支払いができなくなる「資金ショート」に陥ってしまうのです。
あなたの会社はどれ?黒字倒産を引き起こす5つの代表的な原因
私がこれまで見てきた現場では、黒字倒産に陥る企業には共通した原因があります。代表的な5つのパターンを見ていきましょう。
原因1:売掛金の罠(入金サイトの長期化と貸し倒れ)
これは最も多い原因です。特に、取引先の力が強いBtoBビジネスで頻繁に起こります。
- 入金サイトの長期化:
例えば「月末締め・翌々月末払い」のような契約では、商品を納品してから現金化されるまで2ヶ月以上かかります(この期間のことを入金サイトと呼びます)。
この間、人件費や経費の支払いは待ってくれません。実は、売上が伸びれば伸びるほど、先に出ていくお金が増え、資金繰りが苦しくなることがあります。 - 貸し倒れ:
最悪のケースは、売掛金が回収できなくなる「貸し倒れ」です。中小企業庁の調査でも、倒産の直接的な引き金の約2割が販売先の倒産による連鎖倒産というデータがあります。たった1社の貸し倒れが、自社の命運を左右することもあるのです。
(出典:中小企業庁 倒産の状況 2025年10月)
【事例】Web制作A社のケース 大手広告代理店から大型案件を受注し、売上も利益も過去最高を記録。しかし、入金サイトが「納品後90日」と長く、外注費や人件費の支払いが先に来て資金繰りが悪化。そんな中、頼みの綱だった広告代理店が突然倒産。売掛金2,000万円が全額回収不能となり、A社も連鎖倒産寸前に追い込まれました。
原因2:在庫の重荷(売れない資産の増加)
小売業や製造業に多く見られるパターンです。在庫は会計上「資産」として扱われるため、一見すると会社に価値があるように見えます。しかし、売れなければ1円にもならない、現金を生み出さない資産です。
- 過剰在庫:
「セールで安かったから」「欠品が怖いから」と過剰に仕入れた結果、売れ残ってしまうケース。 - 不良在庫:
流行が過ぎたり、型落ちしたりして価値が著しく下がった在庫。これらは倉庫のスペースを圧迫し、管理コストだけがかかる「負の資産」と化します。
【事例】アパレルB社のケース ある年の春、特定のデザインが流行すると予測し、関連商品を大量に仕入れました。しかし予測は外れ、商品は大量に売れ残り。決算書上は在庫という「資産」があるため黒字でしたが、仕入れ代金の支払いができず、銀行からの追加融資も断られ、資金繰りに行き詰まりました。
原因3:過剰な設備投資(回収の遅い支出)
事業拡大を目指して新しい機械や社屋に投資することは重要です。しかし、その計画が甘いと、投資が自らの首を絞めることになります。
設備投資は数百万〜数千万円という大きなお金が一気に出ていきます。金融機関から融資を受けても、その返済はすぐに始まります。しかし、投資した設備が利益を生み出し、投資額を回収できるまでには長い時間がかかります。この間の資金繰りを軽視すると、返済に追われて運転資金が枯渇してしまうのです。
【事例】印刷業C社のケース 生産性を上げるため、最新鋭の印刷機を3,000万円の金融機関から長期借入金を組んで導入。確かに生産性は上がりましたが、期待したほど新規の受注は増えず、売上の伸びが返済額に追いつかない状況に。結果、毎月の返済が重くのしかかり、原材料の仕入れ代金の支払いにも窮するようになりました。
原因4:借入金返済(利益を圧迫する固定支出)
銀行からの借入は事業の成長に不可欠ですが、忘れてはならないのが「元本の返済は、税金を支払った後の利益からしかできない」という事実です。
会計上の「経費」になるのは利息部分だけ。元本返済は経費にはなりません。
例えば、年間利益が500万円の会社が、税金を約150万円払い、残った350万円の中から、年間の元本返済300万円を支払うと、手元には50万円しか残りません。利益が出ているように見えても、現金が全く増えない構造です。
原因5:急な成長の落とし穴(運転資金の急増)
意外に思われるかもしれませんが、会社が最も潰れやすいのは、赤字の時ではなく、売上が急激に伸びている時です。
売上が急増すると、仕入れの増加、人件費の増加、外注費の増加など、先行する支払いが増大します。しかし、売上の入金はその後からやってきます。この「出ていくお金の増加スピード」に「入ってくるお金の増加スピード」が追いつかず、資金がショートしてしまうのです。これが「勘定合って銭足らず」です。
今すぐ実践!お金の流れを改善する7つの具体的な対策
では、どうすれば「黒字倒産」を防げるのでしょうか?難しい会計知識は必要ありません。明日から、いえ、今日から始められる具体的な7つの対策をご紹介します。
対策1:「資金繰り表」の作成とモニタリング
【推定工数: 4h/月、期待効果: 資金ショートリスク回避 大】
多くの経営者が「面倒だ」と敬遠しますが、資金繰り表なくして経営は始まりません。資金繰り表は、会社の未来の現金の動きを予測するなくてはならないツールです。
最低でも3ヶ月先までの現金の入出金予定をすべて書き出しましょう。「いつ」「誰から」「いくら」入金があり、「いつ」「誰に」「いくら」支払うのか。これをやるだけで、「来月の15日に資金が足りなくなりそうだ」といった危険を事前に察知できます。
▶︎▶︎ すぐに使える!プロ監修「シンプル資金繰り表」テンプレート(Excel)をダウンロード
対策2:売掛金の回収ルール徹底
【推定工数: 2h/週、期待効果: 回収期間の短縮】
入金が遅れがちな取引先はありませんか?「請求書を送ったから大丈夫」ではなく、回収までが営業の仕事です。
- 請求書発行を迅速に: 締め日後、即日発行をルール化する。
- 入金サイトの交渉: 新規取引では、可能な限り短いサイト(例:翌月末払い)で契約する。
- 入金遅延のアラート: 支払期日を1日でも過ぎたら、すぐに経理から確認の連絡を入れる。それでも入金がなければ営業担当者が連絡するなど、社内ルールを明確にしましょう。
対策3:定期的な在庫チェックと処分
【推定工数: 8h/四半期、期待効果: 在庫圧縮によるキャッシュフロー改善】
倉庫の奥で眠っている在庫は、お金が眠っているのと同じです。
- 定期的な棚卸し: 少なくとも3ヶ月に1回は在庫をすべてリスト化(棚卸)し、「動いている在庫」と「眠っている在庫」を明確に分けます。
- 処分ルールの設定: 「半年以上売れていない商品は、原価を割ってでもセールで売り切る」「1年以上動きのない商品は廃棄する」など、明確なルールを作り、機械的に実行しましょう。損切りは痛みを伴いますが、未来のキャッシュを生むための重要な経営判断です。
対策4:支払いサイトの交渉
【推定工数: 1h/取引先、期待効果: 資金繰りの安定化】
売掛金の回収を早めるのと同じくらい、買掛金の支払いを延ばすことも重要です。もちろん、無理な交渉は禁物ですが、長年の取引がある仕入れ先であれば、交渉の余地はあります。
「月末締め・翌月末払い」を「翌々月末払い」にしてもらえないか、真摯にお願いしてみる価値は十分にあります。それだけで1ヶ月分の資金繰りが楽になります。
対策5:適切な資金調達方法の検討
【推定工数: 10h〜、期待効果: 資金調達の選択肢拡大】
資金調達=銀行からの融資、だけではありません。状況に応じて様々な選択肢を持ちましょう。
- 制度融資: 日本政策金融公庫や各都道府県が実施している、比較的低金利で審査も通りやすい公的な融資制度を活用する。
- ファクタリング: 入金待ちの売掛金を専門業者に買い取ってもらい、早期に現金化する手法。手数料はかかりますが、急な資金需要に有効です。しかし、一時的な利用だけにする。繰り返し利用しないこと!
- 補助金・助成金: 国や自治体が提供する返済不要の資金。申請の手間はかかりますが、活用しない手はありません。しかし、何か設備投資などが必要な場合は、自社で先にその支払いをして、数か月後に補助金が着金されるので、それまでの間の資金繰りを明確にしておく
対策6:「キャッシュフロー計算書」の活用
【推定工数: 3h/月、期待効果: 経営判断の精度向上】
少し専門的になりますが、税理士に決算書を作成してもらったら、キャッシュフロー計算書(C/S)も出してもらいましょう。これは、1年間で会社の現預金が「なぜ」「どれくらい」増減したのかを示してくれる書類です。
- 営業キャッシュフロー: 本業でどれだけ現金を生み出せているか。ここがプラスであることが絶対条件です。
- 投資キャッシュフロー: 設備投資などでどれだけ現金を使ったか。
- 財務キャッシュフロー: 借入や返済で現金がどう動いたか。
これを見ることで、自社の「お金を稼ぐ力」が客観的に分かり、経営判断の精度が格段に上がります。
対策7:専門家への相談
【推定工数: 1h〜、期待効果: 客観的な視点の獲得】
ここまで読んでも、「自社の場合、何から手をつければいいか分からない」と感じる方もいるでしょう。そんな時は、迷わず外部の専門家を頼ってください。
医者が体の専門家であるように、私たちのような財務コンサルタントは「会社のお金の専門家」です。客観的な視点から問題点を診断し、最適な処方箋を提案できます。初回相談は無料で行っている専門家も多いので、手遅れになる前にぜひ活用してください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 資金繰り表は毎日つけないといけませんか?
A1: 毎日つけるのが理想ですが、まずは週に1回、慣れてきたら月に2〜3回更新するだけでも全く違います。重要なのは、定期的に自社の実際の現預金残高を把握し、資金繰り表の予測値がズレていないかを確認し、続けることです。
Q2: 銀行は赤字だとお金を貸してくれませんか?
A2: 一概にそうとは言えません。一時的な赤字でも、その理由や今後の改善計画を合理的に説明できれば、融資を受けられる可能性は十分にあります。銀行が最も嫌うのは「理由の分からない赤字」と「資金繰りに行き詰まってからの相談」です。
Q3: ファクタリングのデメリットは何ですか?
A3: 手数料が銀行融資に比べて非常に高い点です。また、悪質な業者も存在するため、業者選びは慎重に行う必要があります。あくまで短期的な資金繰り改善のための緊急手段と考えてください!
Q4: 小さな会社でもキャッシュフロー計算書は必要ですか?
A4: 必要です。会社の規模に関わらず、現金の流れを把握することは経営の根幹です。顧問税理士に依頼すれば、通常は決算書とセットで作成してくれます。もし作成してくれない場合は、作成を依頼するか、セカンドオピニオンとして他の専門家に相談することをお勧めします。
Q5: どのタイミングで専門家(税理士など)に相談すべきですか?
A5: 「資金繰りが苦しい」と感じた時点ですぐに相談すべきです。多くの経営者は、支払いができなくなってから慌てて相談に来られますが、それでは打てる手が限られてしまいます。車の定期点検と同じで、問題が小さいうちに相談することが、結果的に会社を守ることに繋がります。
まとめ:利益だけでなく「現預金」の流れを見ることが会社を守る第一歩
「黒字なのにお金がない」という問題は、決して特別なことではありません。私が支援してきた多くの企業が、同じ悩みを抱えていました。
しかし、彼らは皆、この記事で紹介したような対策を一つずつ実行することで、危機を乗り越え、より強固な財務体質を手に入れています。
重要なのは、損益計算書の「利益」という数字に一喜一憂するのではなく、資金繰り表やキャッシュフロー計算書を使って、会社の「現預金」という血液の流れを常に監視することです。
まずはこの記事を参考に、危険度チェックリストを再度確認し、資金繰り表のテンプレートをダウンロードするところから始めてみてください。その小さな一歩が、あなたの会社を10年、20年と続く企業へと導く、大きな一歩になるはずです。