
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
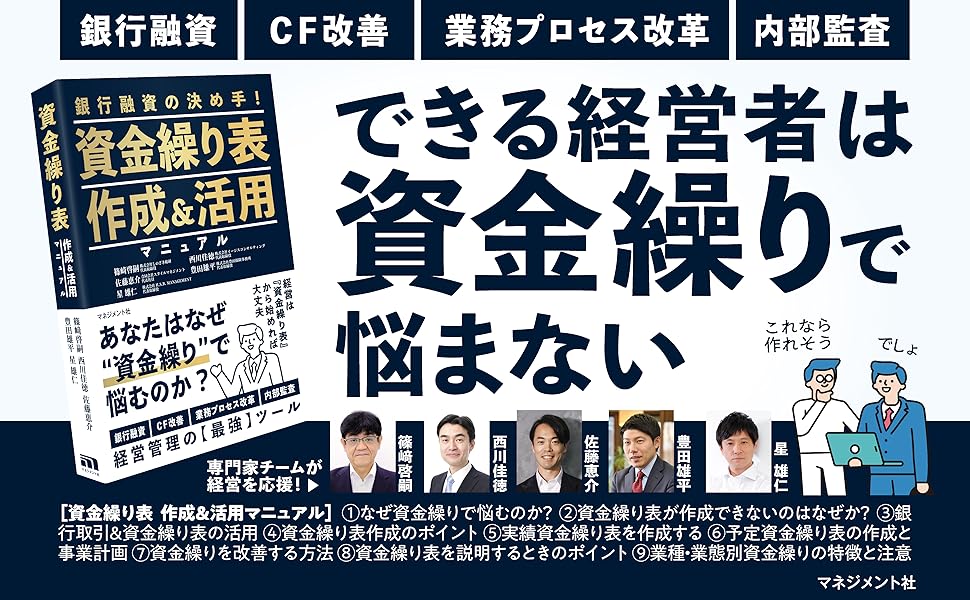
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
運転資金とは、会社を回すために必要な「血液」です。仕入れから売上入金までのズレを埋める資金のことで、これが尽きると黒字でも倒産します。
経営者や経理担当者であれば、「運転資金が足りない」「資金繰りが厳しい」といった悩みに一度は直面したことがあるでしょう。
この記事では、長年、財務コンサルタントとして多くの企業の資金繰りを改善してきた経験から、
運転資金の基本から、自社にいくら必要なのか(目安)、そしてどうやって管理・調達すべきかまで、実務的な視点も交えて徹底的に解説します。

運転資金とは?「会社の血液」と呼ばれる理由
運転資金とは、一言でいえば「事業を継続(運転)していくために、常時必要な手元の資金」のことです。
より具体的には、
商品や原材料を仕入れてから、それが売れて、実際にお客様から代金が入金されるまでの
「タイムラグ」を埋めるためのお金(=つなぎ資金)を指します。
「黒字倒産」の恐ろしさ
なぜ、運転資金が「会社の血液」と呼ばれるのか。それは、たとえ帳簿上(損益計算書)で黒字であっても、この「血液」である現金が底をつけば、会社は倒産してしまうからです。(これを「黒字倒産」と呼びます。)
私が支援したあるIT系企業は、大型案件の受注で売上が前年比200%と急成長していました。しかし、その実態は、先にエンジニア(外注)への支払いが大量に発生し、肝心のクライアントからの入金は「3ヶ月後」という契約でした。
結果、帳簿上は利益が出ているにもかかわらず、手元の現金が枯渇。急いで金融機関に駆け込みましたが、審査が間に合わず、危うく倒産しかけたのです。
このように、利益と現金の流れは必ずしも一致しません。運転資金の管理は、全経営者が最優先で取り組むべき経営課題なのです。
「設備資金」や「経費」との違い
運転資金と混同されやすい言葉に「設備資金」や「経費」があります。
- 設備資金:
- 事業を「拡大」するための一時的な大きな投資(例:機械、PC、店舗、車)。
- 運転資金(ガソリン代)に対し、設備資金は「車本体」と例えることができます
- 経費(販売管理費):
- 事業活動で発生する費用(例:人件費、家賃、広告費)
- 運転資金は「仕入〜入金」のサイクルを回す資金ですが、経費も当然、現金で支払う必要があるため、運転資金(資金繰りの場合)の計算には含まれます。
運転資金はいくら必要? 2つの計算方法と業種別の目安
経営者として最も知りたい「結局、ウチにはいくら必要なのか?」という疑問にお答えします。計算方法は2種類ありますが、まずは簡単な「経常運転資金」の計算を覚えましょう。
1. 【基本】経常運転資金の計算方法(B/Sから計算)
これは、会社のB/S(貸借対照表)さえあれば、誰でも簡単に計算できる方法です。より実務的で、金融機関が融資審査でも使う計算です。
【計算式】
経常運転資金 = 売上債権 (売掛金+受取手形) + 棚卸資産 (在庫) - 仕入債務 (買掛金+支払手形)
この式がなぜ「つなぎ資金」を表すのか、簡単に説明します。
- 売上債権 (プラス): 将来入金される予定だが、まだ現金ではない。
- 棚卸資産 (プラス): 現金で仕入れたが、まだ売れていない(=お金がモノに変わって寝ている状態)。
- 仕入債務 (マイナス): 本来支払うべきだが、まだ支払っていない(=支払いを待ってもらっている状態)。
つまり、「まだ入ってこないお金」+「寝ているお金」-「まだ払わなくてよいお金」が、会社が立て替えるべき「つなぎ資金(運転資金)」となるわけです。
2. 【実務】必要運転資金の計算方法(回転期間から計算)
「回転期間」を用いた計算です。これは「仕入れから入金まで、平均何日分の資金が必要か?」を計算します。
【計算式】
必要運転資金 = (売上債権回転期間 + 棚卸資産回転期間 - 仕入債務回転期間) × 1日あたり売上高
- 売上債権回転期間: 売掛金が入金されるまでの平均日数
- 棚卸資産回転期間: 在庫が売れるまでの平均日数
- 仕入債務回転期間: 買掛金を支払うまでの平均日数
例えば、入金まで60日、在庫が30日、支払いが30日なら、「60 + 30 – 30 = 60日分」のつなぎ資金(売上高の約2ヶ月分)が必要だと分かります。
この日数が長いほど、多くの運転資金が必要になります。
3. 【目安】あなたの会社に必要な運転資金(業種別)
「運転資金は月商の何か月分必要か?」という質問をよく受けますが、コンサルタントとしての答えは「業種と取引条件による」です。
一般論としては「月商の1〜3ヶ月分」と言われますが、これは全くアテになりません。以下に、私が支援してきた企業の肌感覚も含めた業種別の目安と特徴をまとめます。
| 業種 | 運転資金の目安(対月商) | 特徴・アドバイス |
| 小売業 | 0.5〜1.5ヶ月分 | 庫(棚卸資産)が運転資金の大半を占める。特にアパレルなど季節商品は在庫管理が命。 |
| 飲食業 | 0.5〜1.0ヶ月分 | 基本的に現金商売が多く、運転資金は少なめ(マイナスになることも)。ただし、仕入原価(食材)の管理が重要。 |
| 卸売業 | 2.0〜4.0ヶ月分 | 「売掛(入金待ち)」と「在庫」の両方が多くなりがち。入金と支払いの「サイト」管理が最も重要な業種。 |
| 製造業 | 2.0〜5.0ヶ月分 | 材料仕入→製造→販売→入金までのリードタイムが長い。売掛も在庫も多く、最も運転資金が必要な業種の一つ。 |
| 建設業 | 3.0〜6.0ヶ月分以上 | 工期が長く、入金が「完成後一括」なども多いため、巨額の運転資金が必要。特に下請けはサイトが長くなりがち。 |
| IT/サービス業 | 1.0〜3.0ヶ月分 | 在庫はゼロだが、売掛(入金サイト)が長い傾向。また「人件費(外注費)」という巨大な固定費が運転資金の多くを占める。 |
あなたの「運転資金」はどのタイプ?(状況別の分類)
運転資金と一口に言っても、会社の状況によって必要な資金の「性質」が異なります。金融機関と交渉する際も、この分類を理解していると話がスムーズです。
- 経常運転資金
- 常に必要な運転資金。前述の計算で求めたものです。
- 増加運転資金(ポジティブな資金)
- 売上が急増している時に、仕入れや在庫を増やすために「追加」で必要になる資金。
- これは事業成長のための前向きな資金であり、銀行も比較的融資しやすい(黒字倒産のリスク説明は必要)タイプの資金です。
- 赤字補填資金(危険な資金)
- 売上が減少しているにもかかわらず、固定費(家賃・人件費)や仕入の支払いのために必要になる資金。
- いわゆる「赤字補填」であり、最も危険な状態です。早急な事業の立て直し(リストラや経費削減)とセットでなければ、資金調達は困難になります。
- スポット運転資金(季節性・一時的な資金)
- 賞与(ボーナス)の支払い、納税(法人税、消費税)、または季節商品(例:アパレルの夏物仕入れ)のために、一時的に必要となる資金。
- 「いつ、いくら必要か」が明確なため、銀行も対応しやすい資金です。
なぜ運転資金が不足するのか? 5つの主な原因
「最近、なぜかお金が足りない…」その原因は赤字だけではありません。むしろ好調な時こそ注意が必要です。
1. 売上の急激な増加(黒字倒産)
最も陥りやすい「嬉しい悲鳴」です。前述のIT企業の例のように、売上が増えれば、仕入れや外注費も増えます。入金より支払いが先に来れば、売上が増えるほど資金はショートします。
2. 入金サイトと支払サイトのズレ
- 売掛金の入金サイト(例:60日後)が長い
- 買掛金の支払サイト(例:30日後)が短いこの「ズレ(ギャップ)」が大きくなるほど、自社で立て替える運転資金は膨らみます。
3. 過剰在庫(不良在庫)
「いつか売れるだろう」と抱えている在庫は、現金が「モノ」に形を変えて倉庫で眠っているのと同じです。100万円の在庫は、100万円の現金を失っていると認識すべきです。
4. 予期せぬ大きな支出・赤字
- 急な売上減少(大口取引先の喪失)
- 工場の機械が故障し、高額な修理費が発生した
- (建設業などで)赤字工事が発生したこれらは一瞬で資金繰りを悪化させます。
5. 設備投資
運転資金とは別ですが、銀行から「設備資金」として借りずに、手元の「運転資金」で高額な機械を買ってしまうと、日々の運転資金(ガソリン代)が枯渇し、資金繰りが一気に厳しくなります。
運転資金の管理方法と削減のコツ(守り)
資金が足りなくなってから慌てて調達(攻め)するのではなく、まずは日々の「守り」である経営管理体制を整えることが、財務コンサルタントとしての最初のアドバイスです。
1. 資金繰り表の作成(最重要)
「ドンブリ勘定」が一番危険です。最低でも3ヶ月先、できれば6ヶ月~1年先の「未来の現預金残高」を予測する「資金繰り表」を必ず作成してください。
エクセルで、「いつ、いくら入金され、いつ、いくら支払いがあるか」を日々更新するだけで、「来月の25日に資金がショートする!」といった事態を事前に察知できます。
2. 在庫管理の徹底
「適正在庫」を維持し、不良在庫は(たとえ赤字でも)早急に処分(現金化)すること。倉庫の「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」ができていない会社は、例外なく資金繰りも悪化しています。
3. サイトの交渉
言うは易しですが、非常に重要です。
- 売掛先(入金): 既存のサイト短縮は難しくとも、新規取引先とは可能な限り短いサイト(せめて月末締め翌月末)で契約する。
- 買掛先(支払): 支払いを遅らせる交渉は最後の手段ですが、例えば「一部を先に払い、残りを手形に」など、交渉の余地はあります。
4. 経費(固定費)の見直し
売上が減っても、家賃や人件費(固定費)は待ってくれません。聖域を設けず、不要なコスト(サブスク、広告費など)がないか定期的に見直しましょう。
運転資金の調達方法(攻め)
管理してもなお資金が不足する場合、または成長(増加運転資金)のために資金が必要な場合は、以下の調達(攻め)を検討します。
ここで、財務コンサルタントとして非常に重要な、実務上の注意点(罠)について先にお伝えします。
【重要】運転資金は「短期」、設備資金は「長期」が鉄則
資金調達には
「運転資金は短期借入金(返済期間1年以内)、設備資金は長期借入金(返済期間5年~)で借りる」という大原則があります。
- 運転資金: 仕入・入金のサイクル(=短期)で回すお金。
- 設備資金: 投資回収に時間(=長期)がかかるお金。
このように、資金の使い道(回収期間)と返済期間を一致させるのが、財務の基本(=資金使途と返済期間の一致)です。
銀行実務と「資金繰り悪化の罠」
しかし、実務の現場では、この原則が守られないケースが非常に多く見られます。
とくに銀行側が、審査の手間や管理の都合から、本来は短期で回すべき運転資金(前述の増加運転資金やスポット資金)であっても、「とりあえず長期借入金(例:5年返済)で貸し出す」という対応をすることがあります。
企業側は、一時的にまとまったお金が入るため安心してしまいがちですが、これが大きな罠となります。
短期で使い終わるはずの資金のために、長期の返済(元金均等返済など)が始まると、月々の返済負担が重くのしかかります。結果として、一時的に助かったはずが、数ヶ月後から始まる返済によって資金繰りが圧迫されるという、本末転倒な事態に陥る企業を、私は数多く見てきました。
融資を受ける際は、「なぜこの返済期間なのか」を銀行にしっかり確認し、安易な長期借入に頼らないことが重要です。
運転資金に関するよくある質問 (FAQ)
Q1. 運転資金と設備資金の違いは何ですか?
A. 運転資金は事業を「回す」ための日々の資金(ガソリン代)、設備資金は事業を「拡大」するための投資(車本体)です。融資の際も、銀行は明確に分けて審査します。
Q2. 運転資金がマイナスになることはありますか?
A. あります。前述の計算式で「仕入債務(買掛金)」が「売上債権+棚卸資産」より大きければマイナスになります。これは「他人のフンドシで相撲を取っている」状態で、現金商売(飲食店や一部小売)で在庫を持たない業態では、理想的な経営状態と言えます。
Q3. 個人事業主やフリーランスでも運転資金は必要ですか?
A. 必要です。特にITフリーランスなどは、入金が2ヶ月先(60日サイト)も珍しくありません。その間の生活費や経費(PC代、交通費)は、すべて運転資金(=手元の貯金)でまかなう必要があります。
Q4. 「黒字倒産」はなぜ起こるのですか?
A. 帳簿上の「売上」と、実際の「入金」のタイミングがズレるからです。売上が急増し、先に仕入れや外注費の「支払い」が来てしまい、手元の現金が尽きることで起こります。
Q5. 銀行から運転資金を借りる際のポイントは?
A. 「なぜ必要なのか」を明確に説明することです。「増加運転資金(売上増対応)」や「スポット運転資金(賞与)」は説明しやすいです。「減少運転資金(赤字補填)」は、具体的な経営改善計画書がなければ、まず借りられません。
まとめ
運転資金とは「会社の血液」であり、経営者や経理担当者は、その流れ(資金繰り)を常に監視し、コントロールする「心臓」の役割を担っています。
利益を出すこと(PL)はもちろん重要ですが、それ以上に「現金を回し続けること(キャッシュフロー)」が、会社を存続させるためには不可欠です。
この記事を読み終えたら、まずは以下の2点から始めてみてください。
- 自社のB/Sを見て「経常運転資金」を計算してみる。
- 簡単な「資金繰り表」を作り、3ヶ月先の現金残高を予測してみる。
自社の「今」の数字を知ることが、安定した経営への第一歩です。