
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
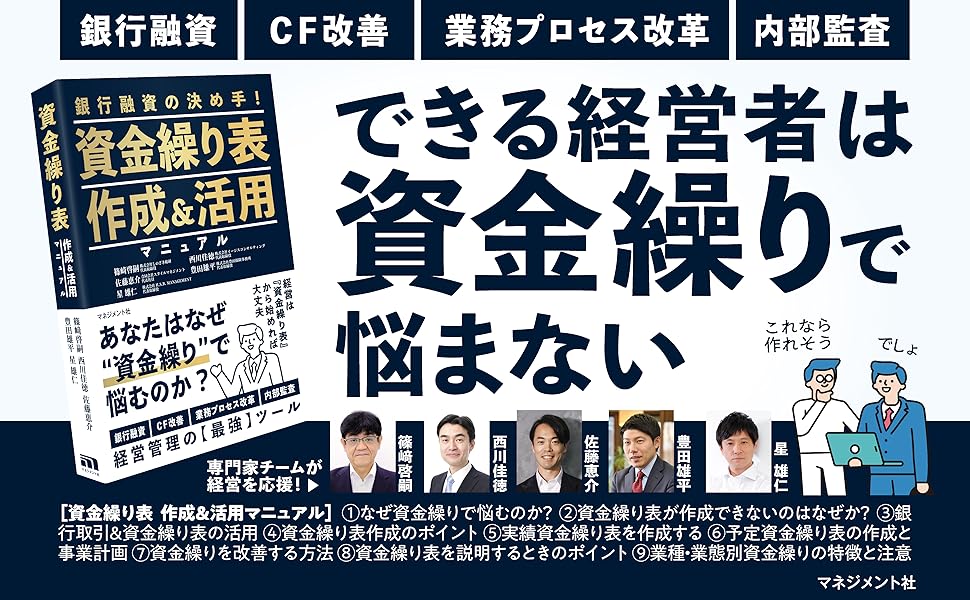
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「経費削減」と聞くと、「コストカット」「我慢」「現場の負担増」といったネガティブなイメージをお持ちではないでしょうか。
しかし、真の経費削減は、単なる「節約」ではありません。
会社の支出構造を見直し、無駄な「浪費」を、未来の利益を生む「戦略経費(投資)」に振り向ける、極めてポジティブな経営改善活動です。
長年、財務コンサルタントとして多くの中小企業の資金繰り改善に携わってきましたが、成長する企業は例外なく、この「コストの組み替え」が上手です。
この記事では、単なるアイデアの羅列ではなく、「メリハリのあるコストの使い方」そのものを変革し、会社を利益体質に変えるための戦略的なアプローチと具体的な手順を徹底解説します。

なぜ経費削減は失敗するのか?よくある3つの理由と対策
多くの企業で経費削減の号令がかかりますが、その多くが中途半端に終わるか、かえって現場の士気を下げてしまいます。まずは、失敗の根本原因を知ることから始めましょう。
理由1: 目的が曖昧(ビジョンなきカット)
最も多い失敗例が、「全社一律で10%カット」といった、目的の曖昧な削減目標です。
なぜ削減するのか(例:新規事業の原資、DX推進、社員への賞与還元)というポジティブなビジョンが共有されなければ、従業員にとっては「一方的に我慢を強いられる活動」でしかありません。
- 対策:経営者が「削減して生み出したキャッシュで、何を実現したいのか」という未来図を明確に示すことが不可欠です。
理由2: 現場のモチベーション低下
必要な経費(例:業務効率を上げるPCスペック、スキルアップのための書籍代)まで一律に削減する「聖域なきコストカット」は、現場の疲弊とモチベーション低下を確実に招きます。
- 対策:削減すべきは「業務の非効率」や「無駄な慣習」であり、従業員の意欲や生産性を下げるものであってはなりません。むしろ、現場から「この業務は無駄ではないか」という改善提案を歓迎し、インセンティブを与える仕組みが効果的です。
理由3: 効果測定と実行が中途半端
「ペーパーレス化推進」「電気のこまめな消灯」といったスローガンだけで終わり、どの施策がどれだけの効果を上げたのかを誰も把握していないケースです。
これではPDCAが回らず、活動はすぐに形骸化します。
- 対策:プロジェクトチームを設置し、経費精算システムなどのツールを活用して「削減額の可視化」を徹底することが重要です。
経費削減の第一歩:コストを「浪費・消費・投資」で仕分ける
戦略的な経費削減の成否は、最初の「仕分け」で決まります。
私がコンサルティングに入る際、まず経営者と管理職の方々にお願いするのは、全経費を「浪費・消費・投資」の3色マーカーで色分けしてもらうことです。
1. 浪費(Waste)とは?
定義:会社の価値(売上・利益)に全く貢献しない、なくすべき支出。
例 :過剰な在庫、使われていないSaaSアカウント、効果の出ていない広告、不要な接待交際費、非効率な業務プロセスが生む無駄な残業代、過剰な印刷コスト。 方針: 即時ゼロを目指す。
【専門家の視点】 あるIT系B社では、管理部門が把握していない「現場契約のSaaS」が大量に存在し、棚卸しした結果、使われていないアカウントだけで年間300万円以上の「浪費」が見つかりました。これは氷山の一角です。
2. 消費(Consumption)とは?
定義:現在の事業を維持するために必要だが、最適化の余地がある支出。
例 :オフィスの家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費、既存の広告宣伝費、ノンコア業務の人件費
方針:最適化(より安く、より効率的に)を目指す。
3. 投資(Investment)とは?
定義:将来の価値(売上・利益)を生み出すために、戦略的に使うべき支出。
例 :人材育成費、R&D(研究開発)費、DX推進ツール導入費、新規事業のマーケティング費、業務効率化システム(経費精算システムやRPAなど)。
方針:最大化を目指す。
ポイント:経費削減の真の目的は、「浪費」をゼロにし、「消費」を最適化して生み出したキャッシュ(原資)を、「投資」に振り向けることです。
【実践編】経費削減アイデア一覧(浪費・消費の観点)
上記の分類に基づき、具体的な経費削減アイデアを解説します。
1. オフィスコストの「浪費」削減と「消費」最適化
- (浪費)ペーパーレス化の徹底
- 会議資料の印刷廃止、電子契約の導入、クラウドストレージの活用。
紙代、インク代、保管スペース(家賃)という三重のコストを削減します。
- 会議資料の印刷廃止、電子契約の導入、クラウドストレージの活用。
- (浪費)未使用の固定電話回線や備品の解約・廃棄
- 使われていない電話回線やリース機器は、即時見直しの対象です。
- (消費)消耗品費の発注プロセス見直し
- 発注窓口を総務部などに一元化する「集中購買」や、相見積もりの徹底で単価を下げます。
- (消費)水道光熱費
- 電力・ガス会社の切り替えは、リスクなく固定費を削減できる即効性の高い施策です。LED照明への切り替えも長期的な効果が出ます。
- (消費)地代家賃
- リモートワーク導入によるオフィス面積の最適化(縮小移転)は、最大の固定費削減策となり得ます。
2. IT・システム関連費の「浪費」削減と「消費」最適化
- (浪費)SaaS・サブスクリプションの棚卸し
- 前述のB社のように、利用実態のないツール、重複機能を持つツールは即時解約します。
- (消費)通信費(法人携帯プラン、インターネット回線)の見直し
- 契約プランが現状の利用実態(データ使用量など)と合っているか、定期的に見直します。
- (消費)IT機器の調達
- 最新スペックが不要な部署では、リースや中古・再生品(リファービッシュ)の活用も有効です。
- (投資へ)経費精算システムやRPAの導入
- 経費申請や請求書処理にかかる「業務工数(見えない浪費)」を削減し、社員をより付加価値の高い業務(投資)へシフトさせます。
3. 人件費・業務プロセスの「浪費」削減と「消費」最適化
- (浪費)非効率な業務プロセスが引き起こす「無駄な残業代」
- 「残業禁止」と号令をかけるのは最悪手です。削減すべきは残業代そのものではなく、残業を生み出す「非効率な業務プロセス」や「無駄な会議」です。
【専門家の視点】 食品卸C社では、毎日2時間かかっていた受発注のFAX処理を、システム化と業務フローの見直しで30分に短縮しました。この結果、月平均20時間の残業削減(浪費の削減)に成功し、社員は「顧客への提案資料作成(投資)」に時間を使えるようになりました。
- (消費)アウトソーシング(BPO)の活用
- 経理の記帳代行や給与計算、コールセンター業務など、ノンコア業務を外部委託することで、社員はコア業務に集中できます。「消費」を最適化し、「投資」時間を生み出す典型例です。
- (消費)採用コストの見直し
- リファラル採用(社員紹介)の強化や、費用対効果の低い採用媒体からの撤退を検討します。
- (投資へ)福利厚生の見直し
- 利用率の低い保養所(消費)などを廃止し、全社員が使えるスキルアップ支援制度や書籍購入補助(投資)に振り向ける方が、従業員満足度と生産性の向上に繋がります。
4. その他(交際費・出張費など)の「浪費」削減
- (浪費)慣習で行っているだけの接待交際費
- 「付き合いで仕方なく」行っているゴルフや会食は、本当に将来の売上に繋がっているか、費用対効果を厳しく検証します。
- (消費)出張旅費規程の整備
- オンライン会議への切り替えを第一選択とし、出張の要否を厳格化します。日当や宿泊費の上限規定(出張旅費規程)の整備も必須です。
- (消費)広告宣伝費
- 費用対効果(ROAS)の低い広告や、効果測定ができていない媒体(浪費に近い消費)は停止し、効果の高いWebマーケティング(投資)に予算を集中させます。
経費削減を成功させる5つのステップ(進め方)
アイデアを実行に移し、成功させるための具体的なステップを紹介します。
STEP1: 現状把握と可視化
まず、自社が「何に」「どれだけ」使っているかを徹底的に可視化します。会計ソフトや経費精算システムのデータを基に、勘定科目ごとに支出を洗い出し、前述の「浪費・消費・投資」に分類します。
STEP2: 削減目標と「聖域(投資)」の設定
「浪費」は100%削減、「消費」は20%削減など、分類ごとに現実的な削減目標を設定します。 最も重要なのは、「投資」に分類した経費(人材育成、R&D、DX推進費など)を「聖域」として明確に定義し、安易に削減対象としないことです。
STEP3: 削減計画の策定と優先順位付け
「効果が大きく、実行しやすい」ものから着手します。 優先すべきは、全社的な合意形成が不要な「浪費」の削減(例:未使用SaaSの解約、電力会社の切り替え)です。
STEP4: 全社への周知と実行
STEP2で設定した「目的(なぜ削減するのか)」と「聖域(投資)」を全社に丁寧に説明します。「我慢」ではなく「未来への投資原資を生み出す活動」であることを共有し、協力を仰ぎます。
STEP5: 効果測定と再投資の実行
削減できた金額を月次で可視化します。そして、その削減額を、STEP2で決めた「投資」先に明確に予算として振り分けるプロセスを実行します。これがなければ、単なる「節約」で終わってしまいます。
経費削減の第二手:「運営費」を工夫し「戦略経費」を増やす
中小企業の経営者様から「投資(戦略経費)に回す余裕がない」というご相談を非常によく受けます。 その場合、私はコスト構造をより大きな視点、すなわち「運営費」「設備費」「戦略経費」の3つで捉え直すことをお勧めしています。
コスト構造の3分類
- 運営費(Opex): 事業を「維持」するためのコスト。人件費、家賃、水道光熱費、消耗品費など。(=消費がメイン)
- 設備費(Capex): 価値が長期にわたる資産コスト。PC購入費、ソフトウェア開発費、オフィスの内装費など。
- 戦略経費(Strategic Cost): 事業を「成長」させるためのコスト。新規事業開発費、大型マーケティング費、DX推進費など。(=投資)
目指すべき姿:「運営費」の効率化と「戦略経費」への転換
多くの企業が、「運営費(消費)」の最適化(=節約)だけで終わってしまいます。 しかし、本当に目指すべきは、経費精算システムの導入(設備費)やBPOの活用(運営費)によって、運営費(消費)を徹底的に効率化することです。
そこで生み出された「社員の時間(人件費)」と「キャッシュ」を、未来の売上を作る「戦略経費(投資)」に再配分する。
これが、会社を利益体質に変える「戦略的コスト最適化」の核心です。
第一歩は「浪費」と「運営費」の可視化から
あなたの会社の「運営費」には、手入力や紙の請求書処理、非効率な会議といった「見えない浪費」がどれだけ隠れているでしょうか?
まずは自社の経費を可視化し、どこに「浪費」が潜んでいるかを把握することから始めましょう。
会社の経費削減に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 経費削減はどの勘定科目から手をつけるべき?
A1. まずは「浪費」に分類されるもの(例:未使用のSaaS、過剰な接待交際費)から即時着手しましょう。これらは削減しても業務に支障が出ないため、合意形成が容易です。次に「消費」のうち、効果が大きく実行しやすい「消耗品費」や「通信費」の見直しが推奨されます。
Q2. 従業員のモチベーションを下げないためには?
A2. 「これは浪費の削減であり、必要な投資は増やす」という目的を明確に共有することです。一方的な「消費」の切り詰めは不満を生みますが、「浪費」をなくすことに反対する従業員は基本的にいません。削減成果をインセンティブ(賞与や研修費)で還元する仕組みも有効です。
Q3. 中小企業でも導入すべき「投資」は?
A3. 「経費精算システム」や「クラウドストレージ」「電子契約サービス」などは、優先度の高い「投資」です。目先の導入コスト(設備費)はかかりますが、長期的な「運営費」(特に管理部門の人件費)の削減と、経費利用の透明化(浪費の抑制)に繋がり、費用対効果が非常に高いと言えます。
Q4. 経費削減とリストラの違いは?
A4. 経費削減は「業務プロセスの見直しや無駄な支出を減らす活動」全般を指します。一方、リストラ(Restructuring)は事業再構築を意味し、その一環として人員削減(解雇)が行われる場合があります。本記事で解説する経費削減は、あくまで業務効率化によるコスト最適化であり、人員削減を目的とするものではありません。
まとめ
本記事では、戦略的な経費削減のアプローチについて解説しました。
- 経費削減の失敗は「目的の曖昧さ」「モチベーション低下」が原因。
- 成功の鍵は、経費を「浪費・消費・投資」に分類すること。
- 「浪費」はゼロに、「消費」は最適化を目指す。
- 具体的なアイデアを「オフィスコスト」「ITコスト」「業務プロセス」で実行する。
- 真の目的は、「運営費」を効率化し、生み出した原資を「戦略経費(投資)」に再配分すること。
経費削減は、決して「我慢」ではありません。自社のコスト構造を見直し、未来への投資原資を生み出すための「戦略的な経営活動」として、ぜひ第一歩を踏み出してください。