
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
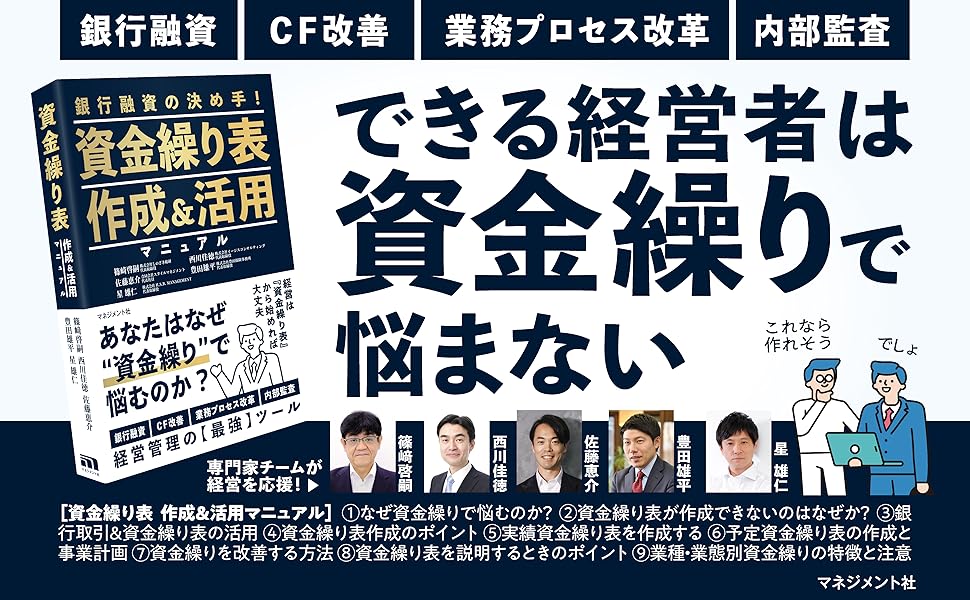
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「事業性評価」という言葉をご存知でしょうか?
近年、金融機関(銀行)が融資を行う際、従来の「担保」や「保証」以上に重視するようになったのが、この事業性評価です。
「事業性評価が重要と聞いたが、具体的に何をみられるのか?」
「評価を高めて、資金調達を有利に進めたい」
本記事では、このような疑問を持つ経営者や財務担当者様向けに、事業性評価の基本から、金融機関が重視する具体的な評価項目、そして評価を高めるための実践的なステップまで、長年財務コンサルティングと資金繰り支援の現場に携わってきた専門家の視点でわかりやすく解説します。
事業性評価とは? ~財務データ、担保・保証に代わる「企業の将来性」評価~
まず、事業性評価が何であるか、その定義から確認しましょう。
事業性評価の基本的な定義
事業性評価とは、
企業の「過去」の財務諸表や担保価値(不動産など)だけに依存せず、その企業が持つ「未来」の可能性、すなわち事業内容、独自の技術力、市場での競争力、経営者のビジョン、そして将来生み出すキャッシュフロー(現金)などを総合的に評価する仕組みのことです。
簡単に言えば、
「その会社の財務諸表には表れない、数字では示せない、定性情報も加味して融資などの判断する」手法です。
従来型融資(担保・保証偏重)との違い
従来の日本の金融機関(特に銀行)の融資判断は、「財務データ」「保全」を最重要視する傾向が強くありました。
- 過去の決算書(財務諸表)はどうか?(過去の実績)
- 万が一返済できなくなった場合、回収できる担保(不動産など)はあるか?
- 経営者個人の連帯保証は取れるか?
これらはすべて「過去」の資産や「万が一の備え」に焦点を当てた評価です。
しかし、事業性評価に基づく融資は、その視点が根本的に異なります。
| 比較軸 | 従来型融資 | 事業性評価に基づく融資 |
| 評価の主軸 | 過去(財務諸表、不動産担保) | 未来(事業の成長可能性、キャッシュフロー) |
| 重視するもの | 担保・保証人の信用力 | 経営者のビジョン、事業計画の具体性 |
| 銀行のスタンス | 回収の確実性(保全) | 事業の成長支援(リレーションシップバンキング) |
| 企業のメリット | 資産があれば借りやすい | 資産がなくても将来性で勝負できる |
私が支援してきた多くのITベンチャーやサービス業の企業は、創業期には大きな担保(不動産など)を持っていません。
従来型の融資では苦戦しがちでしたが、事業性評価が浸透したことで、「技術力」や「ビジネスモデルの独自性」といった無形の資産(=将来性)を評価され、必要な資金調達に成功するケースが格段に増えています。
なぜ今、事業性評価が重要視されるのか?その背景
では、なぜ金融機関はこぞって「事業性評価」を重視するようになったのでしょうか。それには明確な理由があります。
背景①:金融庁の方針転換と「リレーションシップバンキング」
最大の理由は、金融行政を司る金融庁の方針が大きく転換したことです。
かつて金融機関には「金融検査マニュアル」という厳格なルールブックがあり、これが担保・保証を重視する融資姿勢(保全偏重)を後押ししていました。
しかし、このマニュアルが廃止され、金融庁は「企業の将来性を評価し、融資だけでなく経営支援も含めた本業支援(=リレーションシップバンキング)を行うこと」を金融機関に強く求めるようになりました。
銀行側も、単に「おカネを貸す」だけでは低金利下で収益が上がりません。
「企業の成長を支援し、中長期的な取引(融資、手数料ビジネス、ビジネスマッチング等)につなげる」という動機が働いています。事業性評価は、そのための「共通言語」なのです。
背景②:中小企業の変化(担保不足・後継者問題)
融資を受ける企業側にも変化があります。
かつては「土地神話」があり、多くの企業が不動産を担保としていました。しかし、現代では不動産を持たないIT企業やサービス業が経済の主役となりつつあります。また、不動産価値そのものも不安定になっています。
さらに、後継者問題も深刻です。事業承継(M&Aや親族への承継)を行う際、「この会社(事業)には、本当に将来価値があるのか?」を客観的に評価する必要があり、ここでも事業性評価の考え方が活用されます。
金融機関は「何を」見ている?事業性評価の具体的な6つの項目
「では、銀行員はこちらの何を評価しているのか?」
ここが経営者の皆様が最も知りたいポイントでしょう。
事業性評価は「定性面(数字に表れない強み)」と「定量面(数字データ)」の両面から行われます。私が多くの資金調達支援の現場で見てきた、特に重要な6つの項目を解説します。
1.経営者の資質とビジョン(定性)
銀行員が最終的に最も重視するのは「人」、すなわち経営者自身です。
事業計画がどれほど立派でも、それを実行する経営者に熱意や誠実さ、実行力がなければ「絵に描いた餅」と判断されます。
- 経営理念・ビジョン: なぜこの事業を行うのか?将来どうなりたいか?
- 業界経験と専門性: 経営者はその道のプロフェッショナルか?
- 誠実さ: 試算表(月次決算)を毎月提出するなど、約束を守れるか?
- 後継者育成: 万が一の際のリスクヘッジ(後継者や右腕の育成)は考えているか?
【資金繰りアドバイザーの視点】
多くの銀行員が口にするのは、「最後は社長を信用できるかどうか」です。特に厳しい局面(例:コロナ禍や急な売上減)で、隠さずに現状を報告し、対策を一緒に相談できる経営者は、金融機関からの信頼が厚くなります。
2.事業内容と市場環境(定性)「そのビジネスは儲かる仕組みになっているか?」という視点です。
- ビジネスモデル: 誰に、何を、どうやって提供し、どうやって収益を上げているか?
- 市場の成長性: 参入している市場は伸びているか、縮小しているか?
- 競合優位性: 他社ではなく、御社が選ばれる「独自の強み」は何か?(技術力、ブランド、販売網、価格競争力など)
ここで有効なのが、「SWOT分析」や「3C分析」といったフレームワークです。
これらを使い、自社の「強み(S)」「弱み(W)」「機会(O)」「脅威(T)」を客観的に整理し、銀行に説明できる状態にしておくことが重要です。
3.組織体制とオペレーション(定性)
経営者一人のワンマン経営ではなく、「組織」として事業が回っているか、という視点です。
- 従業員のスキルと定着率: 必要な人材が揃っているか?離職率が高すぎないか?
- 管理体制: 経理や総務など、バックオフィスは機能しているか?
- 業務プロセス: 非効率な業務(例:いまだに紙とハンコだらけ)がないか?
- コンプライアンス: 法令遵守の意識はあるか?
【財務コンサルタントの視点(事例)】
ある食品加工業(従業員30名)の支援をした際、銀行から「社長が倒れたら業務が止まるのでは?」と懸念されていました。そこで、工場長への権限移譲と、ベテラン社員の技術をマニュアル化する取り組み(オペレーション改善)を事業計画に盛り込みました。これは単なる効率化ではなく、「事業の継続性(リスク管理)」を評価する重要な定性項目として、融資判断にプラスに働きました。
4.財務状況(定量)
もちろん、従来型の財務分析も行われます。
ただし、事業性評価における財務分析は、過去の結果を責めるためではなく、「なぜこの数値なのか?」という原因と、「今後の改善策」を議論するための材料として使われます。
- 収益性: 売上高総利益率(粗利率)、営業利益率
- 安全性: 自己資本比率、流動比率
- 効率性: 売上債権回転期間、棚卸資産回転期間
決算書(特に「勘定科目内訳明細書」)を見て、「この売掛金は本当に回収できるのか?」「この在庫は本当に売れるのか?」といった「実態(リアル)」を銀行は見ています。
5.キャッシュフロー(定量)
財務コンサルタントとして、私が最も重視する指標がキャッシュフロー(CF)です。
利益(PL)は黒字でも、現金(キャッシュ)がなくなれば会社は倒産します(黒字倒産)。
銀行も同様に、キャッシュフロー計算書(またはそれに準ずる資金繰り表)を厳しくチェックします。
- 営業CF: 本業でどれだけ現金を稼げているか?(最重要)
- 投資CF: 成長のために設備投資などをしているか?
- 財務CF: 借入や返済のバランスはどうか?
営業CFがプラスであることは、事業性評価において最低限クリアしたいラインです。もしマイナスであれば、その理由(急激な売上増に伴う運転資金増など)を明確に説明できなければなりません。
6.将来の事業計画(定性+定量)
上記の1〜5のすべてを集約したものが、「将来の事業計画」です。
これが事業性評価における最重要書類と言っても過言ではありません。
銀行が見ているのは、「定性的な強み(例:独自の技術力)」が、「定量的な成果(例:3年後の売上・利益)」にどう結びつくかのストーリーです。
- 行動計画(KPI): 目標達成のために、いつ、誰が、何をするか?
- 数値計画(収支予測): その結果、売上、費用、利益はどうなるか?
- 連動性: 行動と数値に「根拠」と「一貫性」があるか?
「来期は売上20%アップを目指します!」というだけの計画は「絵に描いた餅」と判断されます。
「新規顧客を月5件獲得するため、営業担当を1名増員し、Web広告予算を月10万円増やす。その結果、売上が20%アップする」という具体的な行動(アクション)と数値が連動した計画が求められます。
事業性評価を高め、銀行融資を成功させる3つのステップ
では、具体的にどうすれば事業性評価を高めることができるのでしょうか。私がいつも経営者様にお伝えしている3つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状把握(自社の強み・弱みの客観視)
まず、「敵(銀行)を知る前に、己を知る」ことがスタートです。
多くの経営者は自社の強みは語れますが、弱み(課題)を客観視できていないケースが見受けられます。
ここでお勧めしたいのが、経済産業省が提供している「ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)」です。
ローカルベンチマーク<経済産業省>
これは、自社の財務情報(6指標)と非財務情報(SWOT分析や事業概要)を入力することで、企業の健康診断ができる無料ツールです。
「ロカベン」を使って自社を分析し、それを銀行に持参するだけでも、「この経営者は自社を客観視できている」という高い評価につながります。
ステップ2:説得力のある「事業計画書」の作成
現状把握ができたら、次はいよいよ事業計画書の作成です。
上記で触れた通り、ここでのポイントは「行動と数値の連動性」です。
- 悪い例: 「頑張る」「強化する」といった精神論が多く、数値目標だけが高い。
- 良い例: 「Aという施策(行動)にB円投資するから、Cという成果(数値)が見込める」という因果関係が明確。
【財務コンサルタントの視点(事例)】
ある飲食業(複数店舗経営)がコロナ禍で苦しんでいました。当初の計画は「全店舗で売上回復を目指す」というものでした。
そこで私から、店舗ごとの収益性を分析し、「不採算のA店は撤退(コスト削減)」「B店はデリバリー強化(投資)」「C店はランチメニュー刷新(行動)」という、選択と集中を行う計画を提案しました。この「課題を直視し、具体的な手を打つ」計画が評価され、銀行は追加融資(資金繰り支援)を決定しました。
ステップ3:銀行との対話(モニタリング)
事業計画書は、提出して終わりではありません。むしろ、提出してからが「事業性評価」の本当のスタートです。
計画通りに進んでいるか、進んでいないならなぜか、どう対策するか。
これを定期的に(最低でも四半期に一度、できれば毎月)銀行に報告し、**対話(モニタリング)**を続けることが極めて重要です。
計画(Plan)→実行(Do)→報告・検証(Check)→改善(Action)
このPDCAサイクルを銀行と共有することで、信頼関係(リレーションシップ)が構築され、次の資金調達や経営支援が格段にスムーズになります。
事業性評価の活用シーンは融資だけではない
これまで主に「銀行融資」の文脈で解説してきましたが、事業性評価の考え方は他の経営シーンでも非常に役立ちまM&A・事業承継における活用
M&A(企業の買収・合併)や事業承継において、会社の価値を算定する際にも事業性評価が使われます。
買い手は、「この会社は、財務諸表に表れないどれだけの価値(ブランド力、技術力、顧客基盤)を持っているか?」を評価します。
売り手(後継者を探す経営者)も、自社の事業の価値を客観的に示すために事業性評価の資料(事業計画書)が役立ちます。
事業再生・経営改善の羅針盤として
業績が悪化した企業の事業再生においても、まずは事業性評価が行われます。
「どの事業が不採算か?」「どの事業に将来性があるか?」を見極め、再生計画(経営改善計画)を策定します。
これは、ステップ1で紹介した「ローカルベンチマーク」による現状把握と同じで、自社の経営改善を進める上での「羅針盤」として機能します。
事業性評価に関してよくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
Q1. 赤字決算だと、事業性評価は必ず低くなりますか?
A. 必ずしもそうとは限りません。赤字の理由(先行投資、一時的な要因など)と、将来黒字化するための具体的な事業計画が合理的であれば評価される可能性は十分にあります。重要なのは「なぜ赤字で、今後どう改善するか」を説明できることです。
Q2. 事業性評価に「点数」はつきますか?
A. 金融機関によっては独自のスコアリングモデルを持っていますが、最終的には定性的な判断(例:経営者の熱意、計画の具体性、将来性)が大きく影響します。明確な点数が開示されることは稀です。
Q3. 評価を上げるために、専門家(コンサルタントや税理士)に相談すべきですか?
A. 必須ではありませんが、客観的な視点での事業分析や、金融機関が納得しやすい事業計画書の作成支援を受けるメリットは大きいです。特に「ローカルベンチマーク」の活用や、銀行との対話に慣れていない場合は有効な手段です。
Q4. 金融庁が推奨する「ローカルベンチマーク」とは何ですか?
A. 経済産業省が提供する、企業の健康診断ツールのことです。財務情報と非財務情報(定性面)を入力することで、自社の経営状態を客観的に把握できます。事業性評価の第一歩として有効です。
Q5. 事業計画書はどのくらいの期間のものを作れば良いですか?
A. 一般的には3年〜5年の中期経営計画が求められることが多いです。特に初年度(単年度)の計画は、月次の行動計画(KPI)まで落とし込むと具体性が増し、高く評価されます。
まとめ
本記事では、「事業性評価」について、その背景から具体的な評価項目、そして評価を高めるためのステップまでを解説しました。
重要なポイントを改めて整理します。
- 事業性評価は、担保(過去)ではなく**「企業の将来性(未来)」**を評価する仕組みです。
- 金融機関は、**定性面(経営者、事業内容)と定量面(財務、CF)**を総合的に見ています。
- 評価を高める鍵は、「現状把握(ロカベン)」と「説得力のある事業計画書」、そして**「銀行との継続的な対話」**です。
事業性評価は、単に融資を受けるためのテクニックではありません。
自社の強みと弱みを直視し、未来に向けた具体的な計画を立て、それを実行・改善していくという、経営そのものです。
この記事が、貴社の資金調達と持続的な成長の一助となれば幸いです。