
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
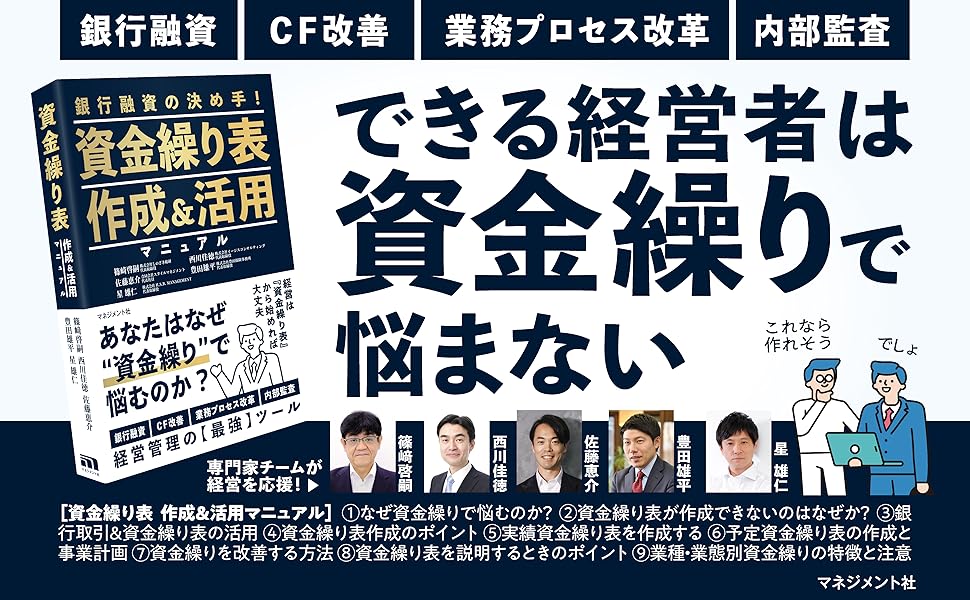
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「今期も黒字だった。利益も出ている。それなのに、なぜか手元の現金が減っていて資金繰りが苦しい……」
企業の経営者や経理担当者の方から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。
この「利益は出ているのに現金がない」という恐ろしい事態は、
会社の成績表である「損益計算書(PL)」上の利益と、実際に手元にある「現金(キャッシュ)」のズレを正しく把握できていないことが原因です。
この“ズレ”を補正し、「会社が本業でおおよそいくらの現金を生み出したか」を把握するための経営指標が、今回解説するフリーキャッシュフロー(FCF)です。
なぜFCFが重要なのか、経営者が最低限知っておくべき簡単な計算方法、そしてFCFがマイナスになった際の具体的な改善策まで、資金繰りのプロがわかりやすく解説します。

フリーキャッシュフロー(FCF)とは? なぜ「利益」だけ見てはダメなのか
フリーキャッシュフロー(FCF)とは、非常に簡単に言えば「会社が自由に使えるお金(の源泉)」のことです。
多くの経営者は、期末に損益計算書(PL)を見て、「今期はこれだけ利益が出た(黒字だ)」と安心しがちです。
しかし、その「利益」は、必ずしも手元にある「現金」とイコールではありません。
銀行融資におけるFCFの重要性:「返済原資」として見られている
なぜ、私たち財務コンサルタントが口を酸っぱくして「利益よりFCFを見ろ」と言うのか。それは、銀行が融資の際に最重要視する指標だからです。
銀行が、企業にお金を貸すとき、知りたいのは「PL上の利益」ではありません。
「結局、この会社は年間いくら現金を稼ぎ出し、ウチへの返済に充てられるのか?」という一点です。
この「借入金の返済能力(=返済原資)」こそが、フリーキャッシュフローなのです。銀行は、PLの経常利益ではなく、このFCF(現金の稼ぎ)を見て、あなたの会社の返済能力を厳しく査定しています。
FCFと「黒字倒産」の恐ろしい関係
「利益」と「現金」のズレを放置すると、最悪の場合、黒字倒産を引き起こします。黒字倒産とは、帳簿上は利益が出ているにもかかわらず、手元の現金が尽きてしまい、仕入れ先への支払いや社員の給与が払えなくなり倒産することです。
【コンサル事例】なぜ黒字なのに倒産?(中堅卸売業A社の例)
私が以前サポートした中堅の卸売業A社は、大口の契約が決まり、その期のPLは過去最高益を達成する見込みでした。しかし、その経営者は青い顔で相談に来られました。
理由は、その大口契約の「支払いサイト(売掛金の回収)」が契約から4ヶ月後だったのです。一方で、仕入れ先への支払いは翌月末。
つまり、売上(利益)は帳簿上立っているが、現金が入ってくるのはずっと先。それなのに、仕入れ代金や人件費、家賃の支払いが先にやってきて、手元の現金がショート寸前でした。
これが典型的な黒字倒産の危機です。売上・利益(PL)だけを見て安心するのではなく、FCF(現金)を見て経営の安全性を判断することが不可欠です。
FCFの簡単な計算方法(経営者・銀行員が見る視点)
「現金の流れ」を正確に把握するのは複雑ですが、経営者や銀行員が「おおよその現金の儲け=返済原資」を把握する(あるいは試算する)ために、損益計算書(PL)を使って簡単に計算できる方法があります。
この記事では、これを「FCF(簡易版)」と呼びます。
FCF(簡易版) = 経常利益 + 減価償却費 - 法人税等
難しく見えるかもしれませんが、一つずつ分解すれば簡単です。
1. 経常利益
損益計算書(PL)にある「経常利益」です。本業の儲け(営業利益)に、利息の受け取りや支払いなど(営業外損益)を加味した、会社の経常的な利益です。
2. + 減価償却費
ここが最も重要です。 減価償却費(げんかしょうきゃくひ)とは、高額な設備(車、機械、PCなど)を購入した際に、その費用を数年に分けて計上する会計ルール上の「費用」です。
例えば、300万円の機械を買っても、PL上は「今月300万円の費用」とはならず、「今月5万円、来月5万円…」と分割して費用計上されます。 この「5万円」は、帳簿上の費用ですが、実際には現金は出ていっていません(お金は買った時(過去)に払っているため)。
「利益」を計算する上では引かれてしまっていますが、手元の現金を計算する上では「実際には出ていっていないお金」なので、利益に「足し戻す」必要があるのです。
3. - 法人税等
利益に対してかかる税金(法人税、住民税、事業税など)です。これは実際に国や自治体に支払う「現金支出」ですので、利益から引きます。
この計算式で出てきた数値が、「税金を払い、本業(および経常的な活動)で手元に残ったおおよその現金(=返済原資)」の目安となります。
【注意点】これはあくまで「簡易版」です
この計算式は、前述のA社(卸売業)の例で挙げた「売掛金(未回収のお金)」や「在庫(倉庫の商品)」の増減は考慮されていません。
もし売掛金や在庫が急激に増えている場合、この計算式でFCF(簡易版)がプラスでも、実際の手元現金はマイナス(資金繰りが苦しい)という事態は起こり得ます。
とはいえ、まずこの「簡易版FCF」を把握するだけでも、PLの利益だけを見る経営からは何歩も前進です。
FCF(簡易版)から見る「手元資金が減る」本当の理由
このFCF(簡易版)で計算した「現金の稼ぎ」は、そのまま会社の貯金になるわけではありません。 この稼ぎ(FCF)は、大きく分けて2つの重要な「支出」に使われます。
- 設備投資(機械の購入、システムの導入、店舗の改装など)
- 借入金の返済(銀行への元本返済)
ここで、経営者が絶対に理解しなければならない、「手元資金が減っていくメカニズム」があります。
手元資金が減る条件 (年間の設備投資額 + 年間の借入金返済額) > FCF(簡易版)
要するに、
「会社から出ていくお金(投資+返済)」が
「会社が稼いだ現金(FCF簡易版)」を上回った場合、
その差額分だけ、あなたの会社の手元資金(現金預金)は減っていくのです。
これが、「黒字なのに現金が減る」の正体です。 (※実際には前述の「運転資本の増減」も加わりますが、まずはこの大枠を理解することが重要です)
【コンサル事例】稼ぎ以上に返済していた製造業B社
私が支援した製造業B社は、経常利益は毎年黒字でした。 FCF(簡易版)を計算すると、毎年 約1,500万円の現金を稼いでいました。
しかし、経営者は「なぜか現金が増えない」と悩んでいました。 調べてみると、過去の積極投資(工場建設)の借入金返済が、年間 2,000万円 もあったのです。
FCF(簡易版)1,500万円<借入金返済 2,000万円設備投資はゼロだったにもかかわらず、本業の稼ぎ以上に返済(支出)していたため、毎年500万円ずつ手元資金が減っていたのです。
この場合、打つ手は
「①FCFを増やす(本業改善)」
「②銀行に返済額の見直し(リスケジュール)を相談する」
しかありません。
フリーキャッシュフローを増やす・改善するための具体的施策
では、FCF(簡易版)がマイナスであったり、投資や返済に対して不足していたりする場合、どうすればよいでしょうか。
施策1:経常利益を増やす(本業の改善)
FCFの源泉は「経常利益」です。
- 売上を増やす
- 粗利率(利益率)を改善する(仕入れ価格の交渉、付加価値の高い商品の開発)
- 固定費を削減する(家賃、人件費、広告費など聖域なき見直し)
施策2:手元の現金を最大化する(運転資本の改善)
※この施策は簡易版FCFの計算式には現れませんが、現金を増やす本質として最も重要です。
- 売掛金の回収サイトを早める
「支払いを30日早めてほしい」という交渉は困難です。実務的には、「(例)10日早く入金してくれたら、請求額から1%割引します」といった早期入金インセンティブを提案する方が、キャッシュの回収を早められるケースがあります。 - 在庫(棚卸資産)を圧縮する
まずは倉庫に行き、「デッドストック(長期間動いていない在庫)」を洗い出してください。それらを赤字覚悟でも現金化(セール販売、廃棄)するだけで、保管コストが浮き、現金も手に入ります。 - 買掛金(仕入債務)の支払サイトを交渉する
「支払いを延ばしてほしい」と交渉するのは、相手との信頼関係を損う可能性があり、最終手段です。まずは自社の経費削減から手をつけましょう。
施策3:税金の最適化(法人税等のコントロール)
いわゆる「節税」です。
役員報酬の最適化、各種保険の活用、税制優遇(中小企業投資促進税制など)の活用で、支払う法人税等を抑えることができれば、その分FCF(簡易版)は増加します。
ただし、過度な節税(例:不要な高級車や保険の購入)は、利益を不必要に減らし、銀行融資(格付け)に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
銀行に返済額の見直しを相談する方法
施策1:複数の借入をまとめて一本化して、返済期間を長くして、月々の返済額を減らす
複数の長期借入金を借りていると、当然、毎月の返済額は増えます。これが現預金を圧迫します。たとえフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスだったとしても、例えば返済額が年間で1,000万とか2,000万など大きければ、それ以上のFCF、すなわち経常利益が必要となってきます。
これ以上、経常利益を増やすのは難しい場合は、
銀行に相談して、複数の長期借入金を一本化して、再度長期借入金を借換えして、返済額を減らすことも可能です。
(既存借入1)当初借入額2,400万円,期間10年,毎月返済額20万円、現在借入残高1,500万円
(既存借入2)当初借入額1,800万円,期間10年,毎月返済額15万円、現在借入残高1,200万円
↓
(まとめて借換)借入額2,700万円,期間10年,毎月返済額22.5万円
当初は、2本の借入で、毎月35万円(年間420万円)の返済額でしたが、
借換後は、毎月22.5万円(年間270万円)の返済額となり、
毎月12.5万円、年間150万円の返済額が減額となりました。
すなわち、年間150万円お金が残るということです。
施策2:返済を止める(リスケジュール)
もう一つは、今借りている返済を全て、一旦止める、いわゆるリスケジュール(リスケ)をするということです。
リスケをすれば、毎月の返済額が0円となります。
その分、お金は出ていきませんので、そのリスケの間に売上・利益を改善し、フリーキャッシュフローを増やしていくのです。
今回は、リスケのことはあまり深堀しませんが、
注意していただきたいのが、リスケ中は新しい借入はできませんので、その分余裕をみてリスケを依頼するようにしましょう。
まとめ
損益計算書(PL)の「利益」だけを見て経営するのは、非常に危険です。利益は出ていても、現金がなければ会社は倒産します(黒字倒産)。
まずは、FCF(簡易版) = 経常利益 + 減価償却費 - 法人税等 という簡単な計算式で、「会社が本業でいくら現金を生み出しているか(=銀行が見る返済原資)」を把握することから始めてください。
そして、その「稼ぎ(FCF簡易版)」が、「年間の設備投資額と借入金返済額の合計」を上回っているかを確認する。 この「現金(キャッシュ)」に基づいた経営判断こそが、これからの時代を生き抜く安全で持続的な経営の第一歩です。
フリーキャッシュフローに関するよくある質問(FAQ)
Q1: 結局、「利益」と「フリーキャッシュフロー(FCF)」は何が違うのですか?
A1: 「利益」は、会計ルールに基づいて計算された帳簿上の儲けです。「FCF」は、その利益から、実際には現金が出ていかない費用(減価償却費)や、実際に出ていく支出(法人税など)を調整した、「実際の手元の現金の儲け(目安)」です。銀行は、このFCFを「返済原資」として見ています。
Q2: 減価償却費を「足す」のはなぜですか?
A2: 減価償却費は、帳簿上(PL)では「費用」として利益から引かれています。しかし、実際には現金が出ていっているわけではありません。手元の「現金」の残高を計算したいので、「(費用として)引かれすぎていた分を、足し戻す」という調整が必要になるためです。
Q3: FCF(簡易版)が年間返済額より少ないと、どうなりますか?
A3: FCF(簡易版) < 年間返済額 の場合、本業の稼ぎだけでは借金を返しきれないことを意味します。設備投資を全くしていなくても、差額分だけ会社の手元資金(現金預金)が減っていきます。この状態が続けば、いずれ資金ショートします。
Q4: この簡易版FCFがマイナスだと、やはり危ないですか?
A4: はい。この記事の計算式 経常利益+減価償却費-法人税等 がマイナスということは、「本業の活動によって現金が減っている」ことを意味します。これは早急な対策(経費削減、売掛金回収など)が必要な危険なサインである可能性が非常に高いです。
Q5: 設備投資と借入金返済は、どちらを優先すべきですか?
A5: 借入金の返済(元本)は契約上の義務であり、止めると「債務不履行」となり会社の信用問題になります。基本的には返済が優先です。FCF(簡易版)からまず年間返済額を引き、その「残った金額の範囲内」で設備投資の計画を立てるのが、安全な経営の鉄則です。