
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
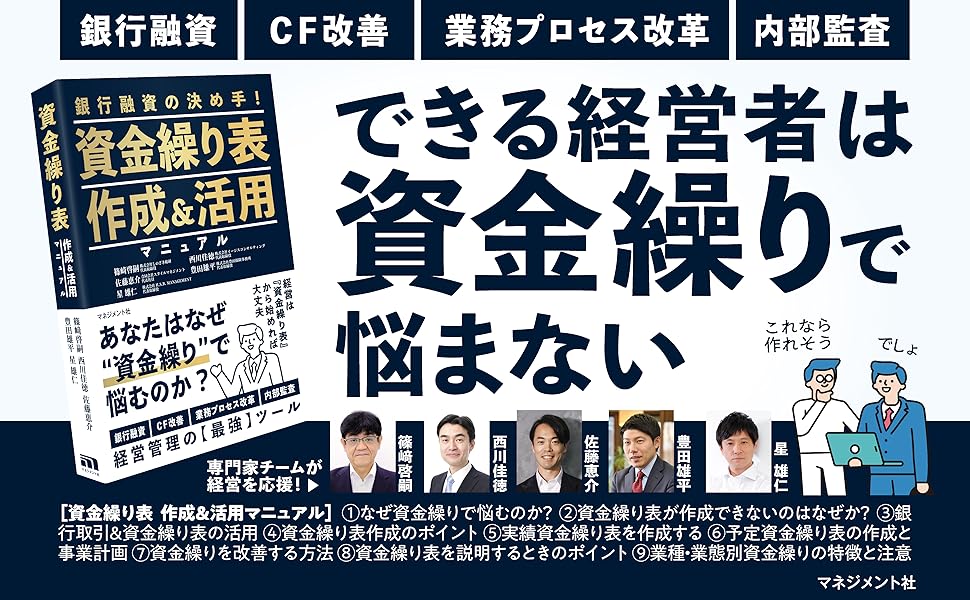
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
資金繰り表は会社の現預金の流れを把握し、黒字倒産を防ぐ非常に重要な書類です。本記事では目的から作り方、分析方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

資金繰り表とは?経営の生命線である現金の流れを管理するツール
「資金繰り表」と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。しかし、これは決して経理担当者だけのものではなく、**経営者自身が会社の健康状態を把握するための”聴診器”**のようなものです。
資金繰り表を一言でいうと
「お金がいつどれだけ入ってきて、いつどれだけ出ていき、どれだけ残ったのかを記録し、将来の現預金残高を予測する表」です。
シンプルですが、会社の血液ともいえる現預金の流れ(キャッシュ・フロー)を正確に”見える化”できる、唯一無二のツールです。
私がこれまでコンサルタントとして多くの企業の経営相談に乗ってきましたが、成長企業が突然失速する原因の多くは、実は「資金繰りの悪化」にあります。売上や利益だけを見て安心してしまい、足元の現預金の動きを見逃してしまうのです。
この記事を最後まで読めば、なぜ資金繰り表が重要なのか、そして明日からすぐに実践できる作成方法と、経営を改善するための分析のコツまで、すべてをご理解いただけます。
なぜ資金繰り表は重要なのか?3つの目的を理解しよう
「利益が出ているからうちは大丈夫」と考えていませんか?それは非常に危険なサインかもしれません。資金繰り表がなぜ重要なのか、3つの具体的な目的から見ていきましょう。
目的1:黒字倒産のリスクを防ぐ
私がキャリアの初期に担当した、あるITサービス企業の話です。彼らは順調に大型案件を受注し、損益計算書(PL)上は過去最高の利益を叩き出していました。しかし、ある日突然「来月の支払いができないかもしれない」と駆け込んできたのです。
原因は、売上金の入金が数ヶ月先である一方、外注費や人件費の支払いが先に発生していたことでした。これが典型的な**「黒字倒産」**の危機です。利益(売上 – 経費)と、手元の現預金(キャッシュ)の動きにはタイムラグがあるため、「勘定合って銭足らず」の状態に陥るのです。
資金繰り表を作成すれば、この利益と現金のズレを事前に把握し、「いつ、いくら現金が不足しそうか」を予測できます。この予測こそが、黒字倒産という最悪の事態を避けるための第一歩です。
目的2:将来の資金ショートを予測し、対策を打つ
資金繰り表は、過去の実績を記録するだけでなく、未来の現金を予測する機能が最も重要です。通常、半年先~1年先の収支、現預金残高を予測します。
例えば、予測をする中で「3ヶ月後に現金残高が大きく減る」ことが分かったとしましょう。原因は、大型設備の購入と従業員の賞与支払いが重なることかもしれません。
これが事前に分かっていれば、
- 金融機関に融資の相談を始める
- 支払先と交渉し、支払時期を遅らせてもらう
- 売掛金の早期回収を営業チームに依頼する
といった先手の対策を、余裕を持って打つことができます。
多くの経営者が資金繰りに窮するのは、問題が起きてから慌てて対策しようとするからです。資金繰り表は、未来のリスクを事前に知らせてくれる「早期警戒システム」なのです。
目的3:金融機関からの信頼を得る
融資を申し込む際、金融機関の担当者は必ずこう質問します。「資金繰り表はありますか?」と。
なぜなら、彼らは「この会社はちゃんと自分たちのお金の流れを管理できているか?」を知りたいからです。きちんと更新された資金繰り表を提出できると、
「この経営者は計数管理能力が高い」
「計画的に経営を行っている」
という強力な証明になり、融資審査において非常に有利に働きます。
逆に、どんぶり勘定で「なんとなくお金が足りなくなりそうなので貸してください」では、信頼を得ることは難しいでしょう。資金繰り表は、金融機関との良好な関係を築くための「パスポート」とも言えるのです。
作成前に知っておきたい!損益計算書(PL)やキャッシュフロー計算書との違い
ここで、よく混同されがちな他の会計書類との違いを整理しておきましょう。キャッシュフロー計算書と損益計算書(PL)との違いを理解することが重要です。
| 書類名 | 目的 | 時間軸 | 特徴 |
| 資金繰り表 | 現預金の過不足を管理する 経営者、財務担当者が利用する | 過去~未来 | 未来の予測がメイン。自社の資金(現預金)管理のために利用する |
| キャッシュフロー計算書 | 一定期間の現金の流れを総括的に示す 金融機関、投資家に提出する | 過去 | 企業のキャッシュフローの状態を把握するために利用する |
| 損益計算書(PL) | 期間中の儲けを把握する | 過去 | 収益と費用を発生時点で計上。 |
一番の違いは「時間軸」です。
損益計算書やキャッシュフロー計算書が過去の実績をまとめた「結果報告書」であるのに対し、資金繰り表だけが「未来の計画書」としての役割を持っています。だからこそ、経営者が日々見るべき書類なのです。
【無料テンプレート付】資金繰り表の作り方5ステップ
理屈は分かったけれど、どう作ればいいのか分からない、という方もご安心ください。
私がコンサルティングの現場で改良を重ねてきた、シンプルで実践的なExcelテンプレートをご用意しました。これを使いながら、5つのステップで作成してみましょう。
[今すぐ使える!専門家監修の資金繰り表テンプレートを無料でダウンロード]
ステップ1:テンプレートを用意する(Excel or 会計ソフト)
まずはExcelテンプレートをダウンロードしてください。最近の会計ソフトには資金繰り表の自動作成機能がついているものもありますが、まずはExcelで手作りし、自分のお金の流れを”体感”することを強くお勧めします。
ステップ2:主要な項目を理解する
テンプレートを開くと、大きく3つのブロックに分かれています。
- 経常収支: 本業による現金の出入りです。「収入(売上入金など)」から「支出(仕入、人件費、経費、税金支払など)」を引いたもの。この経常収支がプラスであることが経営の基本です。
- 財務収支: 資金調達や返済による現金の動きです。金融機関からの借入金は収入、返済金は支出になります。
- 設備収支: 設備投資や補助金収入など、本業以外での特別な現金の出入りです。
これら3つの収支の合計が、その月の最終的な現預金の増減額となります。
ステップ3:前月の繰越残高を記入する
一番上の「前月繰越」欄に、前月末時点でのすべての現金・預金口座の残高合計を記入します。これがスタート地点の残高です。
ステップ4:当月の現金の出入りを実績値で記入する
次に、当月の現預金の出入りを実績ベースで記入していきます。預金通帳や経費精算書を見ながら、実際の入出金額を各項目に埋めていきましょう。
初心者がつまずきやすいのは
「売掛金の回収予定」と
「買掛金の支払予定」の管理です。
ここは営業担当者や仕入担当者と密に連携し、請求書ベースで正確な入出金日を把握することが精度向上のカギとなります。
ステップ5:6ヶ月~1年先の予定を予測値で記入する
ここが資金繰り表の真骨頂です。
まずは、
家賃や人件費、リース料といった毎月ほぼ固定で出ていく「固定費」を先の月まで埋めてしまいましょう。
次に、
見込み客や受注残から「売上入金の予測」を立て、
それに対応する「変動費(仕入など)の支払予測」
を記入します。
そして、支払利息や税金の支払いの予測を記入し、
最後に、毎月の銀行借入の返済額を記入してください。
予測の精度は100%でなくても構いません。まずは正確性は置いておいて、脱完璧主義で資金繰り表をに数字を入力していくことから始めてください。
資金繰りを改善するための3つのチェックポイント
資金繰り表は、作って終わりでは意味がありません。
完成した表を元に、会社のどこに問題があるのかを分析し、改善のアクションにつなげましょう。私がいつもクライアントにお伝えしている、最低限チェックすべき3つのポイントをご紹介します。
チェックポイント1:経常収支はプラスになっているか?
まず見るべきは、本業での稼ぎを示す「経常収支」です。ここが恒常的にマイナスの場合、ビジネスモデルそのものに問題がある可能性があります。借入でなんとか回せていても、それは延命措置にすぎません。
もしマイナスなら、
- 売掛金の回収を早める交渉はできないか?(例:入金サイトを60日から30日に短縮)
- 買掛金の支払を遅らせる交渉はできないか?(例:支払サイトを30日から45日に延長)
- 不要な経費や過剰な在庫はないか?
- そもそも本業の利益がマイナスになっていないか?
といった対策が必要です。
ある飲食チェーンでは、主要な仕入先数社と交渉し、支払サイトを平均15日延長しただけで、手元資金が劇的に改善した事例があります。
チェックポイント2:大きなマイナスが発生する月はないか?
表を数ヶ月先まで眺めて、現預金残高がガクッと減る月がないか確認してください。 多くの会社では、法人税や消費税の納税月、あるいは従業員の賞与支払月に資金が厳しくなる傾向があります。
こうした「資金繰りの谷」を事前に把握しておけば、金融機関にあらかじめ相談し、「つなぎ融資」などの短期的な資金調達を計画的に行うことができます。
チェックポイント3:現預金残高は月商の1.5ヶ月分以上を維持できているか?
最後に、月末の現預金残高を見てみましょう。
業種にもよりますが、一つの安全ラインとして「月商の1.5ヶ月分」の現預金を常に確保できているかを確認してください。これを下回る状態が続くと、急なトラブル(売上減少、大型の修繕など)に対応できず、一気に資金ショートに陥るリスクが高まります。
もし基準を下回っている場合は、利益の一部を内部留保に回したり、長期的な運転資金の調達を検討したりする必要があります。
資金繰り表に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 資金繰り表はいつから作成すべきですか?
A1. 理想は創業初日からです。しかし、思い立ったが吉日。この記事を読んだ今日からでも遅くはありません。まずは過去3ヶ月の実績と、未来3ヶ月の予測から始めてみましょう。
Q2. どのくらいの頻度で更新すれば良いですか?
A2. 最低でも月1回の更新は必須です。これを「月次資金繰り表」と呼びます。資金繰りが厳しい状況の会社や、日々の入出金が多い業種(小売、飲食など)の場合は、「日次」で管理する「日繰り表」を作成することをお勧めします。
Q3. 個人事業主でも必要ですか?
A3. はい、絶対に必要です。 個人事業主は事業用の資金と生活用の資金が混同しがちだからこそ、お金の流れを客観的に把握することが法人以上に重要になります。青色申告の準備も楽になります。