
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント
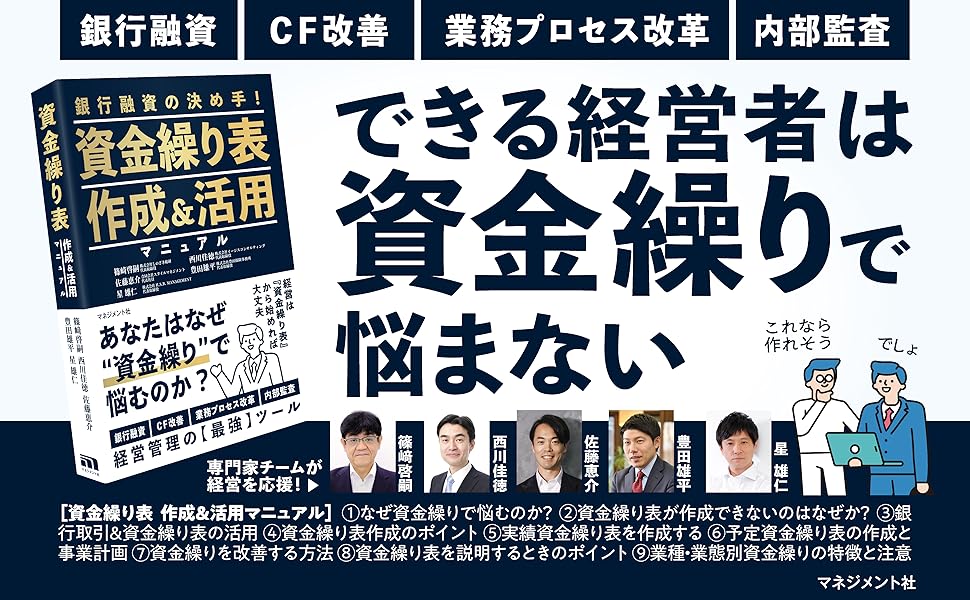
『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
もしかして、うちも危ない?」
その不安を解消します。資金繰り悪化の「前兆」と「すぐできる改善策」を、今すぐ確認できるチェックリストにまとめました。
多くの経営者が「売上はあるのに、なぜか現預金が足りない」という状況に直面します。これが、いわゆる「黒字倒産」の恐怖です。
こういった資金繰りリスクは、ある日突然訪れる災害のように思われがちですが、それは間違いです。リスクは必ず「前兆」として、会社の様々な場所に現れます。
私はこれまで、多くの「手遅れ一歩手前」の企業を見てきました。その経験から断言できるのは、資金繰りの問題は「外科手術(=即時改善)」と「体質改善(=予防)」の両方が必要だということです。
この記事の価値は、自社の危険度を「早期発見」し、その深刻度(フェーズ)に応じた「正しい改善策」までをワンストップで実行できる点にあります。
「うちはまだ大丈夫」と思っている経営者ほど、危険です。手遅れになる前に、このチェックリストで自社の「今」を直視してくだ3さい。

【フェーズ1: 早期発見】資金繰り悪化の「前兆」チェックリスト15選
まずは、自社の健康状態を診断します。これらの兆候が 3つ以上 当てはまったら危険信号です。すぐに【フェーズ2】の行動に移ってください。
最も見逃してはならない、数字に表れるサインです。
財務・経理上の兆候(危険度:高)
(専門家の視点)これが最大の危険信号です。損益計算書(P/L)の「利益」だけを見て、「現金(キャッシュ)」の動きを把握していないのは、残高を見ずにカードを切り続けるのと同じです。
税金・社保は、金融機関が最も重視する支払い項目です。ここに遅れが出ると、銀行の信用評価は即座に「要警戒」レベルに下がります。
業界内で「あの会社は危ない」という噂が広まる最速の道です。一度失った信用を取り戻すのは困難を極めます。
「月末入金だったはずが、翌月5日になった」「大口のA社からの入金が遅れがちだ」といった小さなズレが、命取りになります。
利益が出ていないか、利益以上に現預金が外に流出している証拠です。
これらは高金利であり、銀行からの正規の融資(プロパー融資や保証協会付融資)が受けられなくなっている可能性を示唆します。決算書にこれらの借入が載ると、銀行の評価は著しく下がります。
もちろん業種によりますが、月商の3〜6ヶ月分を超える借入金は「過大債務」と見なされるラインです。そして多くの場合、返済負担が収益を圧迫し始めます。
業務・社内の兆候 (危険度:中)
財務諸表より早く、リスクは「現場」の雰囲気に表れます。
これは非常に生々しい兆候です。私が過去に関与したある卸売業B社では、社長の公私混同(会社の資金の不正利用)に気づいた経理担当者が、責任を負わされることを恐れて退職していました。会社の「金庫番」が去るのには、必ず理由があります。
また別の造園業T社では、社長が入院中に、信頼していた従業員が数千万円を横領していたことが分かりました。経理担当がいてもいなくても横領などが発生することはあるのです。
資金繰りが苦しい会社は、ボーナスの遅配や経費精算の遅れ、給与改定の停止など、必ず社員の待遇に良くない影響が出ます。優秀な社員ほど、その空気を察知して早く去っていきます。
「緊急ではない出張」「成果の出ない接待」が聖域化していないでしょうか。資金繰りに苦しむ社長ほど、対外的な見栄を保とうと交際費を減らせない傾向があります。
倉庫の奥に、いつ仕入れたかわからない商品が眠っていませんか?在庫は「寝ている現金」です。1年以上動いていない在庫は、もはや資産ではなくコスト(保管料)を生む負債です。
経営者の兆候(危険度:高)
最終的に、会社のリスクは経営者自身のリスクです。
業界団体の役職や、異業種交流会などに時間を割きすぎで、本業や経営数字と向き合う時間が減っていないでしょうか?
「経費で落ちるから」と、家族との食事や趣味の道具を会社の経費にしていないでしょうか。金融機関は、必ず決算書の「勘定科目内訳明細書」や場合によっては「総勘定元帳」を精査します。不自然な支出は必ずバレますし、何より社員の士気を著しく低下させます。
数字の裏付けがないまま「えいや」で決断してしまう。あるいは、キャッシュが欲しいがために、赤字とわかっているのに大型案件(出血受注)や低利益な案件(赤字案件)に手を出してしまう。これは典型的な末期症状です。
なぜ資金繰りは悪化するのか?(根本原因の特定)
チェックリストで兆候が見つかったら、その「根本原因」を特定する必要があります。原因を潰さない限り、いくらお金を借りても、穴の空いたバケツに水を注ぐようなものです。
原因1. 成長倒産(黒字倒産)
これは最も回避すべき事態で、経営者の管理ミスです。
- 症状: 売上は急激に伸びているのに、現金が足りない。
- メカニズム:
- 売上が急増する。(例:大型案件の受注)
- 仕入、外注費、人件費(残業代など)の「支払い」が先行する。
- 売上の「入金」は2〜3ヶ月先。
- この「支払い」と「入金」のタイムラグ(ズレ)を埋める現金が尽き、倒産する。
- 以前支援したIT系スタートアップD社は、大型のシステム開発案件を受注し、売上は前年比200%と急成長しました。しかし、エンジニアの採用費(固定費の増)と外注費の支払いが先行し、入金は検収後の「90日サイト」。あっという間に現預金が底をつきました。これは、成長に必要な「運転資金」の予測が甘かったために起きた典型的な事例です。
原因2. 慢性的赤字・売上減少
本業の収益力そのものが低下している状態です。最も抜本的な改革が求められます。
- 症状: 売上がジリジリと下がり続けている。3期連続で赤字だ。
- メカニズム: 売上減少、あるいはコスト高により、P/L(損益計算書)の段階で既に赤字。赤字が続けば、会社の現預金(内部留保)は減り続け、いずれ底をつきます。
- 対策: これは【フェーズ2】のコスト削減と、売上増加(高収益商品の開発、不採算事業の撤退)の両方が必須です。
原因3. 経営(財務)管理体制の欠如
いわゆる「どんぶり勘定」「どんぶり経営」です。
- 症状: P/Lは見ているが、資金繰り表は作っていない。感覚で経営判断している。
- メカニズム: 経営者が「今月いくら儲かったか(利益)」は知っていても、「来月いくら支払いが必要か(現預金の推移)」を把握していません。税金や借入金返済(これらはP/Lの経費にはなりません)といった大きな支出を見落とし、突然の資金ショートに陥ります。
- 対策: 【フェーズ3】で解説する「資金繰り表の習慣化」が唯一の処方箋です。
【フェーズ2: 即時実行】資金繰り改善チェックリスト30選
危険信号を察知したら、即座に行動(キャッシュイン増・キャッシュアウト減)が必要です。優先度(即効性)の高い順に解説します。これらは「外科手術」です。痛みは伴いますが、実行しなければ生き残れません。
A. キャッシュインを増やす(即効性:高)
まず、入ってくる現預金を最大化します。
メインバンクまたは、日本政策金融公庫(特にセーフティネット貸付)にすぐに相談してください。P/Lが赤字でも、「資金繰り表」と「経営改善計画」を提示できれば、融資が実行される可能性は十分にあります。
自社だけで銀行を説得する資料を作るのが難しい場合、我々のような認定支援機関(中小企業診断士や税理士など)と一緒に計画を策定することで、金融機関の信頼を得やすくなります。
工場の隅で眠っている古い機械、使っていない社用車、遊休資産はありませんか?本業は赤字だったとしても、まずは現金化を優先すべきです。
「いつか売れるかも」は禁物です。仕入値の半値でも、現金化できるなら実行します。在庫は保管するだけでコストがかかります。
「月末締め・翌々月末払い」を「月末締め・翌月末払い」にできないか。それが無理なら、一部だけでも前金で貰えないか。プライドを捨てて、主要な取引先に交渉します。
経営者個人の資産を会社に入れる(役員借入金)方法です。ただし、これは一時しのぎであり、根本解決ではありません。
B. キャッシュアウトを減らす(即効性:高)
次に出ていく現金を最小化します。
金融機関に融資やリスケジュール(返済猶予)を相談する際、これが実行されていないと「経営者としての覚悟(身を切る姿勢)」を疑われます。生活できる最低限の額まで一時的に減額する決断が必要です。
追加融資が難しい場合の次善策です。毎月の元金の返済(これを約定弁済と言います)を一定期間ストップ(または減額)してもらい、利息のみの支払いにしてもらう交渉です。返済を止めることは、悪のような風潮があります
タクシー利用を原則禁止にする、成果の出ないWeb広告を停止する、不要な接待をゼロにする。経費の一つ一つを見直し、聖域なく実行します。
「黙って滞納」が最悪の選択です。支払えないと分かった時点で、すぐに窓口に出向き、資金繰り表を見せて「分納(分割払い)」の相談をしてください。誠実な相談には応じてくれます。
A(キャッシュイン増)の売掛金交渉とは逆に、仕入先への支払いを遅らせてもらう交渉です。ただし、これは信用を失うリスクが高いため、Aが不可能な場合の手段です。
C. 中長期で取り組む改善策
上記A・Bで当座をしのぎつつ、体質改善に取り組みます。
- □ 仕入先の見直し・価格交渉
- □ 地代家賃の減額交渉(特に更新時)
- □ 水道光熱費、通信費、保険料の見直し(プラン変更、不要な保険の解約)
- □ 不採算事業・店舗からの撤退
- □ 新規顧客開拓、高収益商品の開発
- □ 従業員の給与体系の見直し(成果連動部分の導入)
- □ リース契約の見直し(不要なコピー機など)
- □ (その他、貴社の業界特有のコスト削減策を10〜15個程度列挙)
D. 注意が必要な資金調達(劇薬)
これらに手を出す前に、必ず専門家に相談してください。使い方を誤ると、即死につながる「劇薬」です。
売掛債権を買い取ってもらうサービスです。即日現金化できますが、手数料が非常に高くなります(年利換算で20〜40%になることも)。
私が支援したある建設業C社は、ファクタリングを「便利なサービス」と勘違いし常用していました。結果、高い手数料が利益を圧迫し続け、我々が介入した時には、本来不要だったはずのリスケジュールが必要な状態でした。緊急避難(例:明日までに現金が足りない)以外での利用は厳禁です。
自社の機械や不動産を一度売却し、同時にリース契約を結んで使い続ける方法です。一時的に現預金は入りますが、売却損が出たり、結果的に高いリース料を払い続けることになり、長期的なキャッシュアウトは増えます。
H3のAで触れた通り、これらは「最後の手段」です。金利が15%前後と高く、返済実績が信用情報に残るため、その後の銀行融資が極めて困難になります。
【フェーズ3: 予防】資金繰りリスクを二度と起こさない経営管理体制
外科手術(フェーズ2)で延命したら、二度と同じ苦しみを味わないための「体質改善(予防)」をすることが経営者の仕事です。
予防1.「資金繰り表」の習慣化
これがすべての基本です。「利益」ではなく「現金」を見る習慣をつけます。
- 何をすべきか:
- まずはExcelの資金繰り表を作ります。
→こちらから資金繰り表のサンプルをダウンロードしてください - 「前月末の現金残高」からスタートします。
- 「収入(売掛金入金、雑収入など)」と「支出(仕入、人件費、家賃、経費、借入返済、税金など)」を項目別に予測します。
- 「月末の現金残高」を計算します。
- まずはExcelの資金繰り表を作ります。
- 鉄則: これを最低3ヶ月先まで予測して作成し、毎月実績と見比べて更新します。これにより、「来月の15日に現金が足りなくなる」といった未来のリスクが可視化され、対策を立てることができるようになります。
予防2. 貸借対照表 (B/S) での安全性チェック
P/L(損益計算書)だけでなく、B/S(貸借対照表)で会社の「体力」をチェックします。
- 流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
- 1年以内に現金化できる資産(流動資産)が、1年以内に支払うべき負債(流動負債)をどれだけ上回っているか。
- 目安: 120%以上(100%を切ると危険水域)
- 当座比率(%) = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
- 流動資産から、現金化しにくい「在庫」を除いたもの(当座資産)で見る、よりシビアな指標。
- 目安: 100%以上
予防3. 定期的な専門家への相談
隠さずに試算表を見せられる「かかりつけ医」を持つことが重要です。
- 決算申告だけを依頼している税理士に、毎月試算表を見てもらい、資金繰りのアドバイスを求めてください(顧問契約の見直しも検討)。
- 金融機関の担当者と定期的にコミュニケーションを取り、会社の良い情報も悪い情報も(早めに)共有する関係を構築してください。
- 我々のような外部の財務コンサルタントを、客観的な第三者の目として活用してください。
資金繰りリスクに関するFAQ(よくある質問)
Q1. 売上は伸びているのに、なぜ資金繰りが苦しいのですか?
A. それは「成長倒産(黒字倒産)」の典型的な兆候です。原因は、売上の入金(例: 60日後)よりも、仕入や人件費の支払(例: 30日後)が先に来ている「タイムラグ」にあります。早急に資金繰り表で収支のズレ(必要な運転資金)を正確に把握し、金融機関からの「運転資金」調達を検討してください。
Q2. 資金繰り表はExcelでないとダメですか?会計ソフトは必要ですか?
A. まずはExcelの手作りでも十分です。とにかく「現金の動きを予測する」習慣をつけることが最優先です。ただし、会計ソフト(例: マネーフォワード クラウド、freeeなど)を導入すると、銀行口座と連携してリアルタイムで残高を把握し、将来予測も自動化できるため、管理体制の構築には非常に有効です。
Q3. 借入金の返済が厳しい場合、まず何をすべきですか?
A. 「リスケジュール(返済条件の変更)」を金融機関に打診することです。絶対にやってはいけないのは、返済を遅延させてから(あるいは無断で)相談することです。返済が苦しいと分かった時点で、試算表や資金繰り表を持参し、「改善努力はするが、一時的に元金返済を待ってほしい」と正直に状況を説明することが、信頼を維持する唯一の鍵です。
Q4. ファクタリングは使っても良いのでしょうか?
A. 緊急避難的な一時利用(例: あと3日で売掛金が入金されるが、明日の支払いが足りない)は許容される場合もありますが、常用は絶対に禁止です。手数料が年利換算で非常に高く、利益を確実に圧迫し、根本的な解決にはなりません。常用すれば必ず経営を蝕みます。
Q5. 税金や社会保険料は、後回しにしても良いですか?
A. 絶対に避けるべき、最悪の選択肢の一つです。 税金・社保の滞納は、金融機関からの信用を即座に失う(=融資が止まる)最大の危険信号です。さらに、税務署は差し押さえの権限を持っており、予告なく売掛金や預金口座を差し押さえることができます。支払えないと分かった時点で、すぐに税務署や年金事務所に「分納・延納」の相談をしてください。
まとめ:リスクは「予測」と「行動」で必ず回避できる
資金繰りリスクは、「兆候の早期発見」と「即時の行動」がすべてです。
この記事の45のチェックリストを使い、一つでも「ドキッ」とした項目があれば、それはあなたの会社が発している重要なサインです。
「まだ大丈夫」と問題を先送りすることが、最大のリスクです。手遅れになり、社員や取引先に迷惑をかける前に、今すぐ行動に移してください。